BLOG
ブログ
-

厨房の中は灼熱!熱中症対策を【店舗の開業なら塊】
猛暑日が続く日本 こんにちは。 株式会社塊です。 今週も月曜日から35度以上の猛暑日が続いています。 ここ数日は、涼しいイメージのある北海道でも40度近くの高温になっているんだとか。 最高気温が25℃以上の日を夏日、最高気温が30℃以上の日を真夏日、最高気温が35℃以上の日を猛暑日といいますが、 名古屋の今日(2025年7月25日)までの夏日は29日、真夏日は26日、猛暑日は13日となっています。 5-7月でこの記録となっているので、ほとんど毎日が夏日以上ということですね。 この猛暑における一番の不安事項はずばり「熱中症」です。 熱中症とは高温多湿な環境下で、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもって体温が上昇することで起こる様々な症状の総称のことを言います。 頭痛や筋肉痛、めまい、吐き気などが代表的な症状で、酷いと痙攣や意識障害などの症状がでます。 最悪死に至る可能性があり、そうでなくても脳に障害が残る可能性があるので十分気を付けなければなりません。 そして、熱中症が起こるのは炎天下だけではありません。 室内でも、夜であっても罹患する可能性があるので十分に気を付けなければなりません。 特に飲食店の厨房は、外よりも温度や湿度が高くなることも。 どのような対策をすればいいのでしょうか。 厨房内での熱中症対策 (1)厨房内にエアコンをつける 特に小さな店舗に多いのがエアコンなしの厨房。 客席のあるホールに設置しているから、厨房にはつけなくても大丈夫だろうと考え、つけない方が多いようです。 しかし、たとえ狭い店舗であったとしても、厨房内までしっかりと冷やされることはまずありません。 厨房内独自のエアコンを設置することが望ましいです。 厨房内という限られたスペースなので、エアコン容量がそこまで大きくなくても対応出来ることもあります。その場合は大分費用を抑えることも出来ますので、ぜひ検討してみて下さい。 (2)2-30分に一度の給水を行う 営業前~営業終了までの間、しっかりと水分補給をするようにしましょう。 一度に大量に摂取するのではなく、2-30分に一度、コップ一杯の水程度の量をこまめにとるようにしてください。 水ではなくスポーツドリンクでも問題はありませんが、糖分の摂りすぎになる可能性があるので、水やお茶が望ましいです。 かなりの発汗が認められるならスポーツドリンクではなく、経口補水液を摂るようにしてください。 (3)しっかりとランチ休憩をとる ランチ時はかき入れ時なので、時間をずらすしかありませんが、しっかりとランチ休憩をとってください。 食事をすることで、塩分やエネルギーの補給ができます。水分だけというのは避けましょう。 また、身体を休めることで熱中症にかかりにくくなります。 通し営業の場合でも、暇を見つけて休憩するようにしてください。 スタッフが複数人いる場合は、交代で休憩をさせるようにしましょう。 (4)ユニフォームに工夫をする 厨房内ではエプロンや調理用白衣、コックコートなどを身につけるお店が多いですが、中に着用する肌着及び洋服に工夫をしてください。 袖や首が詰まっていない、通気性が良く、吸湿・速乾の衣服がおすすめです。 涼感インナーは各社が販売していますが、あくまでも”涼感”を高めるインナー。通気性にはあまり優れていないため、高温多湿下では逆に熱がこもってしまうことも。 綿や麻などの素材でできた肌着や洋服を着用するようにしましょう。 (5)体調チェックシートを用意する 営業開始前に従業員に対して体調チェックを行うといいです。 体調チェックシートを用意して(「体調チェックシート テンプレート」などで検索するとテンプレートがダウンロードできます)始業前に各々に記入を促します。 体調の悪い人は無理に働かせないようにしてください。 営業中でも体調が悪くなればすぐに報告できるような、風通しのいい環境を整えることも大事です。 熱中症だけでなく、食中毒の発生の予防にも繋がりますので、普段から行うといいでしょう。 まとめ 先日発表された三か月予報によると、8月、9月、10月も例年より高温になるそうです。 しっかりと対策を行い、無理はせずに営業を行ってください。
-

キッチンカーの始め方【店舗の開業なら塊】
キッチンカーVS実店舗 こんにちは。 株式会社塊です。 近年注目を浴びている飲食店の業態の一つに「キッチンカー」があります。 営業場所や時間を定めることなく、日本全国どこでも行くことができ、好きな時間に営業することが出来ます。 また、開業資金も安く抑えることが出来るので、今人気の開業形態になっています。 しかし、実店舗に比べて認知をしてもらうのが難しかったり、集客が難しいというデメリットもあります。 どちらが初心者の飲食店開業に向いた形態なのか、詳しく見てみましょう。 キッチンカー実店舗開業費用安い比較的高い営業時間自由固定開業場所自由固定経費安い比較的高い提供物自由度が低い自由度が高い開業までの期間短い長い それぞれ長所・短所がありますね。 キッチンカーは開業費用が安く、開業までの期間も短く、 営業場所や営業時間が自由で、運営にかかる経費を抑えることもできます。 しかし一方で、仕込み場所や販売場所の狭さから提供物が限られる、衛生管理が難しいといったデメリットがあります。 また、夏場は車内の温度が極端に上がるため営業が大変です。雨や雪、極端な寒さや暑さのもとでは集客が難しいなどの天候に左右されることも多く、 また、県を跨いで営業する場合、各地で営業許可証を得なければならないので手間がかかります。 販売を許可されている場所にも限りがあり、その場所はしばしば争奪戦になることも。 簡単に始められる分、ライバルが多くなりがちなのも忘れてはいけません。 ただ、費用や期間のメリットは勿論、開業してからも試行錯誤が出来たり、経費を抑えることができたりなど、開業リスクが低いのは事実です。 どのようにキッチンカーを開業したらいいのか流れをみてみましょう。 How To スタート キッチンカー キッチンカー開業までの流れを見てみましょう。 ①事業計画書の作成 これはどの開業形態でも共通して行うことですね。 コンセプトや提供物・サービス、かかる費用、売上予測などを立てましょう。 この計画書を基に必要ならば融資を受ける準備をしてください。 ②キッチンカーを探す いまは、中古のキッチンカーも多く販売されておりこちらを使用するのも手です。 また、リースなどを行っている会社もあるのでそちらも検討してみるといいでしょう。 新品のキッチンカーを購入すると300万円-600万円が相場になります。 そこに厨房機器などの内装設備工事費、外装の装飾費などがかかることになります ですが、実店舗の内装工事費用を考えたら大分安く抑えることができます。 ②出店場所の確保 自由に移動して販売できるとは言え、拠点を決めるのも大事です。 拠点を一つ定め、時にはイベントやお祭りに出店するというスタイルが一番オーソドックスで無駄がなく、おすすめです。 特に拠点地にはビジネス街がおすすめです。 拠点を決めたら土地の所有者に交渉してみましょう。 キッチンカー車内は狭いので、必要に応じて仕込み場所の確保も行ってください。 ③営業許可証の取得 提供内容や資金、キッチンカーがそろい、拠点も決まったら営業許可証を取得します。 拠点となる地域の管轄保健所に申請して取得します。 地方自治体ページに案内がありますのでそちらを確認してみましょう。 各自治体によって販売可能地域があり、仕込み場所の基準なども設定されているのでしっかりと確認してください。 ④開業 営業許可証を取得したら、いざ開業です! キッチンカーは実店舗よりも集客・マーケティングが大変な傾向にあるので、ここからが本番です。 広告やSNSアカウントの開設、HPの開設やグルメサイトの掲載などを行っていきましょう。 ファンがつくと、SNSで出店日と出店場所を勝手に探して来場してくれるので、こうなってしまえば楽です。 まとめ いかがでしたか。 開業の流れを見ても、実店舗よりも大分工程が少ないことがお分かりだと思います。 デメリットも多々ありますが、何より魅力的な開業のしやすさ。 キッチンカーという選択肢を考えてみるのはいかがでしょうか。
-

決算を迎え、第4期へ【店舗の開業なら塊】
6月決算月を終えて こんにちは。 株式会社塊です。 2025年6月に決算を迎えて第3期を終え、株式会社塊は第4期目へと突入しました。 決算前にバタバタすることもあまりなく、穏やかに新しい期を迎えることが出来ました。 これも偏に協力会社を始めとしたお付き合いいただいている法人の皆様、そしてお客様のおかげです。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 さて、第4期に入りましたが、今期はまず新しく「レジンテーブル製造・販売」事業を開始いたします。 電気工事業から始まった弊社ですが、いまや内装一式工事を請け負い、様々な商業施設、店舗、住宅に携わらせていただいております。 さらにレジンテーブル、一枚板など家具事業を始めることによって、一歩進んだ空間プロデュースを行い、より満足いただけるような内装をご提案します。 事業計画書からレシピ作成、オペレーション、保険関係から内装一式、オーダー家具まで、建築のことはすべて塊にお任せください! クラフトチーム塊&クラフトテーブル槐 株式会社塊(かたまり)には、一丸となって皆で仕事をしていくという意味が込められています。 また、建築という職業と、土へんに鬼で「塊」という武骨な漢字のイメージが合致しているのもお気に入りです。 そのような事情を背景として、新規事業であるレジンテーブル製作販売業には「槐(えんじゅ)」という名前を付けました。 木へんに鬼で塊との親和性を持たせ、かつ槐(エンジュ)というのは木材の一種であるため、新規事業との関連性も持たせました。 また、槐は、しばしば「延寿」とも書かれ、長寿や安産、出世を願う縁起の良い木とされています。 これからレジンテーブルが皆様に愛され、長く使用して頂くためにもピッタリの名前になりました。 また、レジンテーブルだけでなく一枚板テーブルもお任せください。 一枚板とは一本の樹木から切り出される、継ぎ目がない木の板のことを言います。 耐久性が高く、長く使えることが魅力で、一枚板ならではの美しい木目や色合いなどのデザイン性も魅力です。 実際、私も実家では一枚板のテーブルを置いているのですが、購入してから既に30年以上経っているようです。しかし、劣化することなく綺麗な状態で今現在も使用出来ています。 確かに、合板や集成材の木材テーブルは安価ですが、長く使用できることなどを考えると一枚板のほうが長い目で見るとお得になることもあります。 今現時点で、16種ほどの木材の種類を取り揃えておりますが、それ以外にお好みのものがございましたら仕入れることも可能ですので、ご相談ください。 もうすぐレジンテーブル専門「槐」のHPが完成します。 また、インスタグラムを始めとしたSNSでは沢山の作品を載せていきます。 塊&槐 インスタグラム→Instagram もちろん内装施工例は今後も載せていきますので、是非チェックしてみて下さい! また、公式LINEもございます。 塊&槐 公式LINE→公式LINE お電話やメールでもお問い合わせは随時受け付けておりますが、公式LINEでももちろん受け付けております。 レジンのことをもっと知りたい、気になるというお問合せでも構いません◎お気軽にご連絡ください。 HPが完成したらまたこちらでも告知いたしますので、しばらくお待ちください。 晩夏にはもっといろいろな情報をお届けできると思いますので、こちらも今しばらくお待ちください!
-

レジンテーブルの製作販売を始めます!【店舗の開業なら塊】
レジンテーブルとは? こんにちは。 株式会社塊です。 「レジンテーブル」という家具を聞いたことはありますか? 何人かに聞いてみたところ、認知度は1割程度といったところでしょうか。 また、実際に現物を見たという方は1人もいませんでした。 近年注目されているレジンテーブルですが、日本における認知度はまだまだのようです。 レジンとは日本語で「樹脂」を意味します。テーブルは机ですよね。 つまりレジンテーブルとは、レジンと木材が組み合わさって出来た机のことを言います。 樹脂は今日、様々な分野で活躍しています。 例えば、歯の詰め物や入れ歯、エアコンの配管と壁の隙間を埋めるためのコーキング、ジェルネイル、アクセサリーなどなど…意外に身近なところに存在します。 大きく分けてレジンの種類は2種類あり、UVレジンとエポキシレジンと呼ばれています。 UVレジンは主にアクセサリーや歯医者で用いられるレジンで、UVライト(紫外線)を当てることによって硬化します。 数秒~数分UVライトに当てるだけで硬化するので、扱いやすいレジンになります。 一方、エポキシレジンは主剤と硬化剤を混ぜ合わせることで硬化します。これは化学反応によるものです。 数時間から数日程度かけて硬化するので、管理は大変ですが、その分強度に優れ、気泡が入りにくいなどの特長もあります。 レジンテーブルに使用するレジンはエポキシレジンです。透明度が高く、その透明度を保ったまま厚みを出すこともできます。 そんな樹脂が木材と合わさると、ガラスと木が組み合わさったような何とも不思議な魅力のあるテーブルになるのです。 レジンテーブルのご紹介 では、どのようなテーブルなのか実際にお見せしたいと思います。 弊社のレジンテーブル事業部門「槐(エンジュ)」が実際に製作したテーブルになります。 こちらは、海をイメージして作成したレジンテーブルです。 濃い色の部分と薄い色の部分がグラデーションのようになっており、海溝の表現も出しました。 濃い部分も透明感があるのがお分かりだと思います。 こちらのテーブルの厚さは5-6㎝ほどありますが、その厚さ分ずっと透明感を保ちます。 こちらは透明なレジンに青色を付けているので見えませんが、もし透明なまま作ったら、地面が見えるくらいの透明感がこの厚みでもだせるのです。 左右の緑は乾燥した藻で、レジンの中に埋め込んでいます。このように、固形物を中に入れることも出来ます。 こちらは製作途中のレジンテーブルです、【クラロウォルナット×オレンジ色レジン】で製作しました。 厳密にはオレンジ色だけでなく赤色や緑色も混ぜており、色の調合が可能なのでどのような色でも作ることが出来ますよ。 このように色を組み合わせ、立体感を持たせることによって、火山の溶岩のような雰囲気を作り上げました。 こちらはレジンの分量が多めのテーブルですね。 オレンジ~黄色のような複雑な色合いですが、濃い色を重ねて流し込むことによって、このように透明感を出さずにマットな質感にすることも可能です。 木とレジン色が似通っているため平面的に見えますが、綺麗な木目がアクセントとなり、奥行きが生まれています。 木材の周りに緑色を入れたことによって、木の存在感も出ていますよね。 まとめ いかがでしたか? もうすぐレジンテーブルの展示場が完成予定ですので、ぜひ実物を見にいらしてください。 テーブルというよりもアートな一点物のこの家具は、きっと生活を彩ってくれるはずです。
-
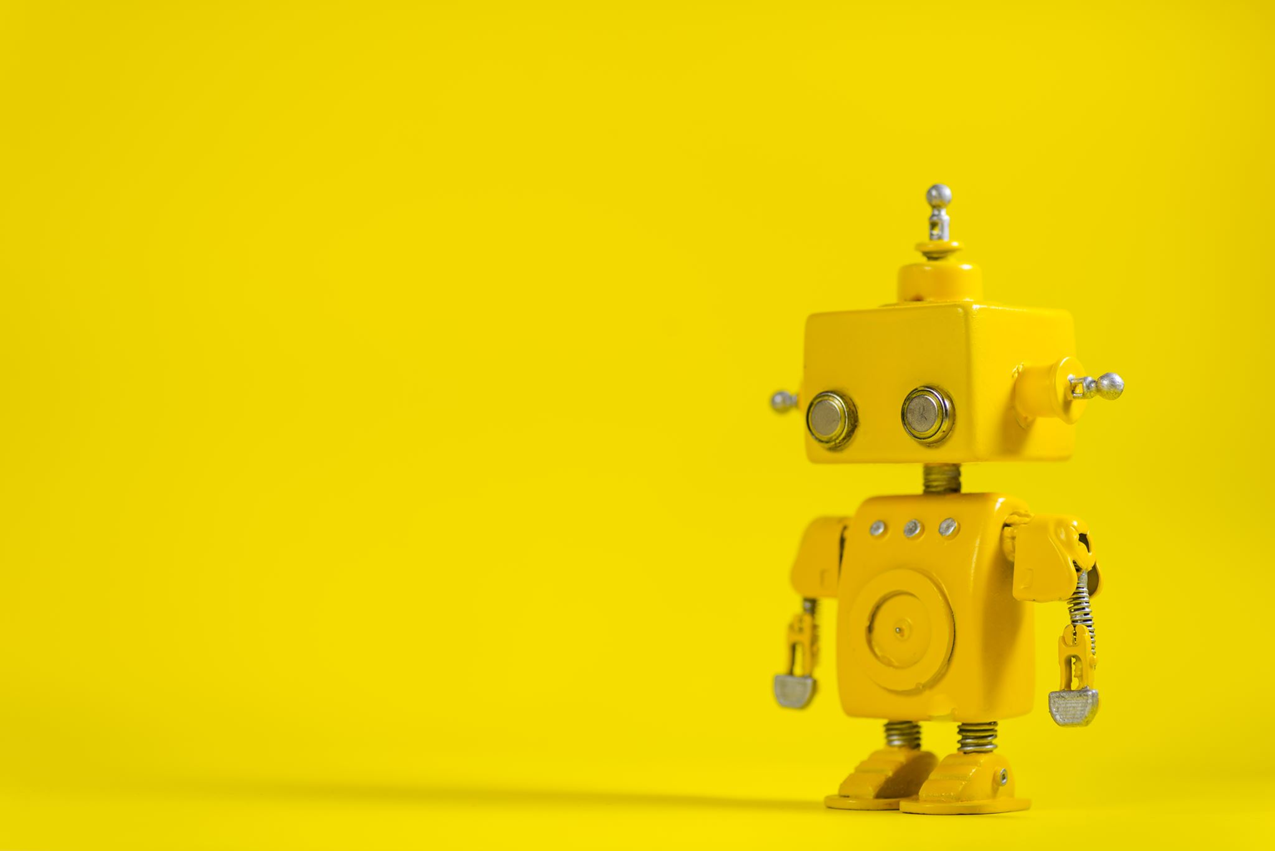
店舗経営にAIを活用しよう【店舗の開業なら塊】
低いAIの利用率 こんにちは。 株式会社塊です。 先日、ランチをしていると、隣の席にいた若い男性グループがAIの話題で盛り上がっていました。 また、先週訪れた定食屋さんの店長さん(女性、30代ほど)は、夏休みのプランをAIに相談して決めて貰い、グランピングに行くのだと楽しそうに話していました。 このHPブログも、「AIを使っていますか?」と聞かれることがよくあります。 このブログにおいてAIを利用したことはありませんが、プライベートではChatGPTなど生成AIを利用しますし、別に反対だという訳ではありません。 このように、会話の話題に上がるくらい、最近ではAIが身近なものになってきました。 テレビのインタビューによると、小中学生が恋愛相談や人生相談でChatGPTを利用するらしく、若年層には学業や仕事での利用よりも、プライベート利用の需要が大きいようです。 生成AIは、今やより身近な何でも話せる存在として確立するまでになりました。 ところが、2024年最新の調査で、生成AIを使っている(使ったことがある)割合はたった9.1%だそう。出典:総務省「デジタルテクノロジーの浸透」 米国が46.3%、中国が56.3%、ドイツ34.6%であるのに比べると、日本はまだまだデジタルテクノロジー、とりわけAIの浸透が遅いことが分かります。 ここまで周囲で話題に出るようになっても、実情はまだまだというところでしょうか。 AIがもたらす情報は、全てが正しいとは限りませんので吟味が必要ですが、上手に使えば作業効率をグッと高めてくれるテクノロジーです。 店舗経営に必須のメールでのクレーム対応やSNSの投稿文、ブログ記事、どのようにマーケティングをしていくのか、売上を上げていくのかなどの戦略方法まで、 自分では思いつかないような切り口から提案してくれることがあります。 ぜひ生成AIを取り入れて、店舗運営に役立てましょう。 店舗経営におけるAIの活用法 (1)クレーム対応の文章作成 クレームはSNSの口コミや電話で受けることが一番多いですが、メールで送られてくることもあります。 電話の際の対応はマニュアル化して掲示しておくといいでしょう。 SNSの口コミやメールの際は、生成AIでの文章作成が生きてきます。 ChatGPTなどの文章生成AIに、受け取ったクレームの文章を添付しその返信を考えるよう指示します。 もしその回答が気に入らなければ、「もっと誠意が伝わるように」「もっと柔らかい口調で」など指示を追加します。 クレームへの返信文章は考えるだけで精神的に疲れる作業なので、このような業務はAIに振ってしまいましょう。 自分で考えるよりもより良い文章を作ってくれますしね。 (2)SNSやブログの投稿文作成 SNSの投稿文章や店舗ブログの記事内容を考えて貰うことも出来ます。 SNSはできるだけ毎日投稿したいところですが、なかなか文章を考えるのが手間ですよね。 そんな時に役立つのが生成AIです。 載せる予定の写真を添付して、文章を作成してもらいましょう。 集客をしたいのか、新商品の案内をしたいのか、日常を紹介したいのか、どのような目的をもって文章を構成してもらうのか指示を出して、生成を依頼します。 大体2-3案出してくれるので、気に入った文章を選びましょう。 インスタグラムで、など具体的なSNS名も記載すれば、#ハッシュタグの内容も考えてくれます。 (3)商品・サービス名などのネーミング 新しく開発した商品やサービスのネーミングも生成AIに任せてみましょう。 自分では思いつかないようなネーミングの提案をしてくれるはずです。 詩的に、もっとかわいらしく、覚えやすいようなもので、略して呼べるようなもので、などの指示を追加してしっくりくるまで生成してもらいましょう。 金額決定も利益率や原価を設定したうえで考えてもらうといいですよ。 (4)レシピ作成 レシピは基本的には自分やスタッフで試行錯誤して作り上げるのが鉄則ですが、煮詰まった時にAIを使うのはアリです。 何か足りない、と感じたときに+αする調味料や食材のアイディア出しをしてもらいましょう。 そこからさらにアレンジを加えることも出来ますし、海外の調味料などの意外な提案は閃きにも繋がります。 (5)売上アップ戦略やマーケティング戦略立案 どのように集客するのか、認知を得ていくのか、売上を上げて安定させるためにはどうしたらいいのかなどの「マーケティング戦略」や「売上戦略」を立ててもらうことも出来ます。 SNSの効果的な活用法やポスティング、動画配信やテレビCM、プレスリリースなどあらゆる広告宣伝手段を考えてくれます。 自分の業種業態、顧客層の情報をいれ、条件に合致するようなマーケティング案を提案してもらってください。 売上金額や経費金額を載せれば売上業績のグラフ作成をしてくれるので、それをもとに売上を上げる戦略を立てるよう指示してみましょう。 自分でも思い付くような案であったり、納得がいかなければ、「もっと掘り下げてください」「もっと詳細な戦略をお願いします」「誰も思いつかないような戦略をお願いします」など条件を追加すれば、よりクリエイティブな案を提案してくれるでしょう。
-

インスタグラムでフォロワーを増やすには?【店舗の開業なら塊】
インスタグラムは最も有効なSNSのひとつ こんにちは。 株式会社塊です。 近年、テレビは「オールドメディア」と揶揄され、その影響力が弱まっています。 神戸の市長選しかり、SNSは強大な力を持つようになり、国の情勢を動かすまでとなりました。 電通の調査によると、2022年にインターネット広告費がテレビ等メディア広告費(テレビ、雑誌、ラジオ、新聞)を初めて上回り、 さらに2024年には1兆円以上の差をつけ、インターネット広告はテレビ広告の1.5倍以上の規模となりました。 いまや企業のマーケティングに欠かせない「インターネット広告」。 情報発信メディアの人気や影響力もテレビからSNS等に移り変わっています。 そのような状況を背景にして、小さな店舗や個人から大企業に至るまで、SNSアカウントを持つことが大事になっています。 新商品やイベントの告知、企業や店舗自身の認知など、現代マーケティングには必須のSNSアカウントからの発信ですが、その中でも影響力を持つSNSの二大巨頭がインスタグラムとXです。 どちらも1投稿内に複数の写真を掲載することができ、文字を添えることが出来ます。 大きな違いは、インスタグラムは写真がメインで、Xは文字がメインとなる点。 ビジュアルで視覚に大きく働きかけるインスタグラムは、Xよりも企業マーケティングに向いていると言えるでしょう。 絵や写真など画像での宣伝は、情報の伝わり方が文章よりも速く強烈で、記憶にも残りやすいという特徴があります。 また、ある調査によると、画像は文字の7倍、動画は5000倍もの情報を伝えられるとも言われています。 リール動画や画像の投稿がメインとなるインスタグラムは、最も効果的にサービスや製品を宣伝することが可能なSNSと言っても良いでしょう。 インスタグラムでフォロワーを増やすには? インスタグラムでのマーケティング効果が特に発揮されるのは、飲食店や美容サロン(ネイル、ヘアー、メイクアップなど)です。 ぜひインスタグラムアカウントを作って、集客を進めていきましょう。 しかし、ここで問題があります。それはフォロワーについてです。 インスタグラムを始めた当初はフォロワーが数人しかつかないはずです。沢山のアカウントをフォローしたとしても、フォローバックされる確率はそこまで高くありません。 また、むやみやたらと顧客層でないアカウントや、お店として適切でないアカウントをフォローすることは、お店の信用を損なうことに繋がりかねません。 確かに、インスタグラムは効果的なSNSではありますが、そもそも質の高いフォロワーがいないとどれだけ魅力的な投稿をしても効果を得ることが出来ないのです。 では、どのようにして質の高いフォロワーを増やせばよいのでしょうか? ①魅力的な投稿を行う 先ほど、どれだけ魅力的な投稿をしてもフォロワーが居なければ意味がないと言いましたが、魅力的な投稿無くしてフォロワーを増やすことはできません。 卵が先か鶏が先か、という議論はよくされますが、この場合は圧倒的にまず「魅力的な投稿」が先です。 自分のアカウントのホームを覗いてくれた時に、「フォローしたい」と思ってもらわなければいつまで経ってもフォロワーが増えることはありません。 まずは魅力的な投稿をすることを心がけましょう。 魅力的な投稿をするためにはまず、どのようなコンセプトでアカウントを育てていくのか決めなければなりません。 コンセプトを決めて、それに沿って写真を投稿しましょう。 文章はそこまで長くない方がいいです。 投稿時間にも気を付けましょう。通勤通学の時間帯が一番ユーザーの目に留まりやすいので朝7時前後、夕方18時前後の投稿がおすすめです。 また、画像投稿のみでなくリール動画やストーリーズ機能も駆使しましょう。 載せたストーリーズは、ハイライトにまとめることもお忘れなく。 投稿についたコメントに返信したり、ハートのリアクションを返すことも大事です。 顧客だけでなく、協力業者などとも積極的にSNS上で交流すると良いでしょう。 インスタグラムで直接仕入れ先を見つけたりする人も今は増えています。 ②投稿にハッシュタグを記載する 投稿には必ず「#ハッシュタグ」を入れて下さい。 投稿や自身の店舗に関連性のあるハッシュタグを選んで記載してください。 ハッシュタグランキングを確認したり、ハッシュタグの予測変換で投稿数が多いハッシュタグを探したりなどを行い、人気のあるハッシュタグを載せましょう。 #名古屋 #名古屋カフェ など、地名を入れたハッシュタグが効果的です。 商業圏内の人にアプローチするためにもぜひ取り入れて下さい。 また、多すぎるハッシュタグは逆効果となる場合があります。10個以内に収めましょう。 ③相手のアカウントにいいねorフォローをする 潜在顧客となるアカウントを探す場合は、お店のペルソナをまず設定しましょう。 ペルソナとは、自身の商品やサービスを利用するであろうもっとも典型的な顧客のことを言います。 例えば、内装にも凝ったオシャレカフェのペルソナは10-20代女性となります。 その人はどのような職業に就き、どのあたりに住み、どのような趣味があり、休日には何をするでしょうか。 そのように具体的に想像し、そのペルソナの情報をインスタグラムで検索します。 厳選してフォローやいいねを押していきましょう。 協力会社などを見つける場合、例えばカフェで出すサラダの野菜を直接農家さんと知り合って仕入れたいとします。 「愛知 農業」「愛知 農家」「農業ファーム」などで検索すると良いでしょう。 愛知県内には農家さんが多数いらっしゃいますが、やはり都心部の名古屋市には少ないので、「名古屋 農業」と検索するよりも「愛知 農業」の方がおすすめです。 多数のフォローをしていると、スパムアカウントだとみなされる可能性があります。 また、企業やお店のアカウントとしては、なるべく「フォロワー>フォロー」という形をとった方が良いので、あまりフォローは増やさない方がいいです。 フォローをせずともフォロワーを増やす方法はあるのでしょうか? それが、「いいね」をすることです。大体3投稿に1づつ「いいね」をしましょう。 「いいね」をするとそのアカウントに「〇〇さんがいいねしました」という通知が流れます。 そのお知らせをもとに自分のアカウントホームに来てもらい、フォローをしてもらうというのがおすすめです。 そのときに、①の魅力的な投稿がなければフォロワーを獲得できませんので、しっかりと内容を作りこんでおきましょう。


