BLOG
ブログ
-

株式会社塊 近況報告【店舗の開業なら塊】
大阪支社開設からはや3ヶ月 こんにちは。 株式会社塊です。 業務拡大に伴い、2月1日に大阪支社を開設しました。 大阪門真に事務所を出してからはや3ヶ月。 大阪での施工数は10を超えました。 また、電気工事士1名、事務員1名が入社しました。 現在は大阪支社長を中心に、順調に運営しております。 名古屋からも月に1回以上支社へ出向くことで、きちんと連携も密に取れております。 先週は名古屋のメンバー全員で大阪に行きました。 全員が顔を合わす機会を設けるのはなかなか難しいですが、 電話やオンラインミーティング等を活用するだけでなく、このように直接会う機会も設けながら 意思疎通に問題がないようにしております。 インテリアアドバイザーの資格を取得しました! 弊社代表と社員1名がインテリアアドバイザーの資格を取得しました。 インテリアアドバイザー資格とはその名の通り、 店舗や住宅の内装・インテリアに関してアドバイスをするための資格で、 インテリアの知識・技術を備え、それを実務で活用できる技能を有していることを認定します。 色の種類やもたらす効果、カーテンの種類や壁材・床材の種類、 天井の種類、照明について、文様や模様、人間工学などなど その範囲は多岐に渡ります。 インテリアはセンスによるところが大きいのでは? と思われる方もいるかと思います。 しかし、センスとは基礎の上に成り立つものです。 なぜ黄色の差し色が紫色なのか?これは実は色の相環図というものが関係あり、 紫と黄色は補色関係という色相環での対面に位置します。 感覚的にこの色が合う!という裏付けにはこのような論理的事実が隠されているわけですね。 このように今後はもっと知識を裏付けにしたご提案が出来るかと思います。 内装のご相談、改装や改修のご相談お待ちしております。 もうすぐ決算です 弊社塊の決算月は6月です。 そこで2期目を終えることになります。 決算までは少しバタバタしがちですが、 体調に気を付けて頑張って参ります。 決算還元でなにかイベントが出来ないかを考えておりますので、ご期待ください。
-

HACCPを遵守しよう【店舗の開業なら塊】
HACCPとは? こんにちは。 株式会社塊です。 飲食店開業を考えている方なら絶対に知っておきたいHACCP(ハサップ)。 聞いたことはありますでしょうか。 このHACCPの順守が日本では2021年6月1日より義務化されました。 飲食店を現在経営されている方はご存じかもしれませんが、 まだまだ知名度が低いのも事実。 開業前にしっかりこの手法について学んでおきましょう。 HACCP(ハサップ)とはH:Hazard(危害要因)A:Analysis(分析)C:Critical(重要、必須)C:Control(管理)P:Point(点) つまり、食品等を扱う事業者は食中毒や異物混入などの危害要因の把握と分析を行い、 それらの危害を除去するために食品を扱う全工程を管理し、 安全性を確保しようとする手法のことを言います。 一言だと、「食品の衛生管理を徹底しましょう」といったところでしょうか。 もともと飲食店、その他食品を扱う業者では 特に衛生管理には気を付けているところが多かったのですが 今まで義務化されてはいませんでした。 上記に記したように2021年6月に義務化されたことによって、 いまはHACCPに則った衛生管理が求められています。 現在これは各都道府県がそれぞれ条例に定めているのですが、 もし違反した場合には、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので 十分に注意が必要です。 HACCPの具体的な取り組み方 では、実際に飲食店においてはどのようにHACCPに則った管理を行えばよいのでしょうか? 厚生労働省がそれぞれの業種・業態ごとに手引書を作成してくれていますので見てみましょう。 ▶HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書 (1)衛生管理計画の策定 ①原材料仕入れルートの安全性担保 ②冷蔵・冷凍庫の温度確認 ③器具や設備等の洗浄・消毒・殺菌 ④トイレの洗浄・消毒 ➄従業員の衛生・健康管理 ⑥衛生的な手洗いの実施 ⑦食材の衛生的な保存・管理方法の徹底 (2)計画に基づく実施 (1)で定めた計画に基づいて、スタッフ全員が順守できるように手引書などを掲示し共有する (3)確認・記録の実施 終業後に実施の結果を記録します。 衛生管理の実施記録チェックシートを従業員ごとまたは キッチン、トイレ、ホールごとに準備し、記入するようにします。 トイレなどにたまに清掃チェックシートなどが貼られている飲食店がありますが こういった飲食店はきちんとHACCPに沿った衛生管理が出来ているのでしょうね。 (4)振り返りの実施 従業員が記入した(3)のチェックシートを確認しましょう。 ポイントのチェック以外にも、問題点があれば共有します。 もし、重要な問題の発生や同じ問題が繰り返し発生していたときは 原因究明に努めて、衛生管理計画や手順書の見直しを行います。 そして従業員への再周知・教育を行いましょう。 (5)衛生管理記録の保管 これらの手引書、チェックシートを保管しておきましょう。 1年間程度は保管し、保健所から提出を求められた場合は従いましょう。 まとめ いかがでしたか? トイレの清掃や手洗いの実施など、当たり前だと思えることかもしれませんが 同じレベルの清浄を全スタッフに求めるのは意外と難しいものです。 その際にこのようなマニュアルやチェックシートがあれば、 同程度の水準を求めやすく、おろそかになることも少ないでしょう。 しっかりと衛生管理を徹底して、安心・安全なお店の運営を行ってくださいね。
-

開業前にやっておきたい競合店舗の調査【店舗の開業なら塊】
競合店舗の事前調査をしよう こんにちは。 株式会社塊です。 開業前には様々準備が必要ですが、そのなかでも競合他店を調べるのは大事です。 お客さんからの評価は得られているのになぜか売り上げが上がらない…。 そんな時その裏には競合他店のキャンペーンなどが隠れているかもしれません。 さらに競合店舗の調査は、事業計画書作成の際にも記入しなければならないような大事なものなので、 「なんとなくこんな感じ」「こういうふうなお店だろう」 などの感覚的な調査ではなく、しっかりとどのようなお店なのか見極めることが大事です。 そのように競合他店の調査を行うことによって、 自分のお店の強みをさらに強化して弱みを補ったり、さらなる差別化を図ることが出来たり コンセプトの明確化にも役立ちます。 自分が出店している地域の競合店舗を調査して、より良いお店作りを目指しましょう! 競合店舗調査のHOW TO では、どのように競合店舗の調査を行うと良いのでしょうか? 順を追って見てみましょう。 ①出店地域の競合店舗をリストアップする 同じ区内で見てしまうと、区によっては範囲が広すぎるので、 徒歩や車で行ける大体~3㎞圏内くらいを確認しましょう。 都心部では競合になってくるお店は徒歩圏内のものになりますので、 この限りではありません。 大体~800mくらいの範囲内で考えればいいでしょう。 ②リストアップした競合店の分類分けをする 例えば、あなたがイタリアンレストランの開業を考えている場合、 ①の作業で全てのイタリアンに関するお店をリストアップします。 そこからバル、高級価格帯のイタリアン、ファミリーレストランなど 分類分けを行います。 あなたがもし客単価1万円ほどのレストランの経営を考えている場合、 バルやファミリーレストランは同種の飲食店ではありますが、 これらは競合店舗にはあたりません。 考えるべきは「高価格帯のイタリアンレストラン」のみです。 ③分類したジャンルの内、競合になりそうなお店に実際に足を運ぶ 先ほどの例で言うと、客単価1万円想定のお店の開業を考える際には、 同価格帯のお店だけでなく、もう少し幅をもたせて 客単価5千円から2万円ほどの中価格帯~超高価格帯のお店に行ってみましょう。 そこで実際に●客層●メニューの種類と単価●お店の内装や雰囲気 などをメモします。 携帯電話のメモ機能等を上手く使用しましょう。 ④競合店の分析をする 実際に見て感じた競合店舗の分析をします。 それぞれの店舗の強みと弱みを書き出しましょう。 例えば以下のように書き出します。 強み●内装が明るくて雰囲気が良い、過ごしやすい●家具からカトラリーにいたるまで一流●特別な経験をすることが出来る●店員が知識豊富で料理やお酒のよさが伝わりやすい●ソムリエが在中している 弱み●駅から遠い●駐車場が併設されていない●階段が急でバリアフリーでない●隣の会話が聞こえやすい●BGMが合っていない●メニューの種類が少ないなんでも結構ですので、とにかく細かい所まで書き出しましょう。 このように分析を行うことによって、圏内の競合他店との差別化を図ることが出来ます。 他店の弱いところをもカバーするような、オリジナルなお店作りを目指しましょう「!
-

ロゴにこだわろう!【店舗の開業なら塊】
世界の有名なロゴとその価格 こんにちは。 株式会社塊です。 みなさんは世界的に有名なあのロゴがいくらで作成されたかご存じですか? ロゴというと、 例えばNIKEだと一筆で描いたようなあの印象的なマークに「NIKE」の文字です。 Googleだとそのまま「Google」の文字列で、 PUMAだと名前の由来にもなったピューマという動物のシルエットと「PUMA」の文字です。 コカ・コーラは「Coca cola」の筆記体のようなデザインだし、 フジテレビは目のようなマークにカタカナで「フジテレビ」。 どの企業もロゴは割とシンプルで、素人でも描けるのでは…といったようなものが多いですよね。 しかし、記憶には確かに残る。 このようにロゴの詳細を羅列しましたが、 この時私はインターネットでそのロゴを調べてから記したのではなく、記憶を辿って書きました。 わざわざ調べずとも分かるくらいのシンプルさとインパクトがあります。 では、私でも描けるのでは…と思ってしまうこのロゴたち、 デザイン料はいくらかかっているかご存じですか? 例えばGoogleのロゴデザイン料は無料。 なぜなら創業者のセルゲイ・ブリンが無料のデザインソフトで作成したため。 NIKEのロゴデザイン料は$35。日本円で5000円くらいです。 デザインを専攻していた大学生のキャロライン・デヴィットソンに時給$2で制作を依頼し、 彼女は17.5時間で制作したため、17.5時間 ×$2=$35というわけです。 では次に、ペプシのロゴデザイン料を見てみましょう。 なんとその額$100万!日本円で言うと1億円くらいです。 球体に赤と青、白色のラインが用いられた印象的なデザインは、 デザイン資料が27ページにも及び、その製作期間はなんと5ヶ月! 黄金比や万有引力の法則が用いられ、 この球体を3Dにした際には人の感情に訴求するような効果もあるんだとか…。 こんなに奥深いデザインだとは知りませんでしたよね。 お次はアクセンチュアというコンサルティング会社のロゴデザイン料を見ましょう。 こちらはアイルランドに本拠地がある世界的なコンサルティング会社ですが、 知らないという方もいるかもしれませんので、まずはロゴから紹介したいと思います。 こちらになります。 見たことありますでしょうか? さてこのロゴデザイン料、お幾らくらいだと思いますか? なんとその額$1億! 日本円で言うと100億円くらいです。 え!?文字の上に「>」マークがあるだけでは?と思いますよね。 この「>」には「Greater than」つまり「より優れている」という意味が込められています。 以前より優れて、他社と比較して優れてなどいろいろな意味にとれますが、 このマークひとつに大きな意味が込められているんですね。 しかしこちらはロゴへの報酬というよりは、 このデザインを使用して法的に問題がないかというチェックにお金がかかったようです。 お店の顔となる看板やロゴ いかがでしたか? たかがロゴ、されどロゴ…。企業によっては数億円以上のお金をかけて作成するようなものなのです。 それはひとえに、より印象深く人々に認知・記憶してもらうため。 そして、従業員に愛着を持ってもらうためにもロゴは必要になってきます。 お店でも、一番に目に入るのがそのお店のロゴや看板です。 いわばロゴは企業・店舗の顔ということですね。 かなり前になりますが、「人は見た目が9割」という本が流行りました。 そのタイトル通り、人は人と対峙したときに顔(正確には顔立ちや雰囲気、声のトーンなど全体の雰囲気など総合的な見た目のことを指します) で相手の性格や自分と合う・合わないなどを判断してしまうそうなのです。 これは何も人対人の時だけではなく、人対モノやお店に対しても言えます。 ですから、ロゴや看板には力を入れた方がいいのです。 出来るならばデザイナーにロゴ制作を依頼してください。 実はこれ、なかなかやっている人が少ないのです。 こんなところにお金をかけなくても…と思いがちですが、 ぜひそういうところほどお客さんに見られている・記憶に残りやすい と考えてこだわってみて下さいね。
-

お店を格上げ!デザイナーズチェア【店舗の開業なら塊】
デザイナーズチェアをお店に取り入れる こんにちは。 株式会社塊です。 先日はデザイナーズ照明をご紹介しました。 今日は有名なデザイナーズチェアをいくつかご紹介したいと思います。 照明も椅子も、デザイナーズのものはお店に取り入れるだけで グッとオシャレな印象になります。 値は張りますが、その分デザイン性が高いため 内装をシンプルにして、家具をこのような高価なものにすることも可能です。 この場合、最終の店舗施工費で比べるとそこまで大差がなくなるかもしれません。 どのような雰囲気のお店にしたいのか、事前にしっかりコンセプトを作りこみながら 内装のアイディアには、このようなデザイナーズ家具も選択肢に入れてみてはいかがでしょうか? 代表的なデザイナーズチェア ●チャールズ・レニー・マッキントッシュの「ヒルハウス」 この椅子は1903年に、建築家のマッキントッシュが 友人のイギリスにある邸宅「ヒルハウス」の主寝室専用にデザインしたものです。 ラダーバックチェアとも呼ばれています。 ラダー=梯子の名の通り、背もたれ部分が梯子のようなデザインになっています。 モダンでオシャレ、すっきりとしているのに存在感のある一脚です。 ●ヘーリット・トーマス・リートフェルトの「ジグザグチェア」 建築家で家具デザイナーでもあるリートフェルトが1934年に オランダにあるシュレーダー邸のために制作したこの「ジグザグチェア」は そのシンプルさから「椅子の究極のかたち」とも言われています。 4枚の木版からなるため見た目以上に丈夫で、安定感があります。 色も赤・青・黄・木目などさまざまで、どのような空間にも合わせやすいデザインです。 ●ミヒャエル・トーネットの「N.14 チェア」 ドイツの家具職人であるトーネットが1860年にデザインしたこの椅子は、 後ろ脚と背もたれ部が1本の木から形成されています。 これは曲木技術という木に高温の蒸気をあてるなどして望みの曲線を描く技術です。 シンプルで汎用性が高く、強度も高いため当時はビストロの椅子として普及しました。 通称カフェチェアとも呼ばれ、カフェからレストランまでどんなシーンにも合います。 6つのブナ材のパーツで構成されるため、分解して輸送することが出来ます。 組み立ても楽で、デザイナーズチェアとはいえ上2つよりも値段がグッと下がります。 ●ハンス・コーレイの「ランディチェア」 スイスのデザイナーであるハンス・コーレイが1938年に製作した椅子です。 アルミニウムで作られているため大変軽く、耐久性にも優れます。 背もたれ部から座面にかけて91個の穴が開いており、 写真のように雨に打たれても雨水が溜まりません。 特にアウトドアに向いている椅子になります。 テラス席など外に空間を設けているお店には特におすすめです。 アルミの酸化防止加工が施されていたり、 スタッキング(椅子を重ねること)が可能なので収納にも場所をとりません。 まとめ いかがでしたか? 上記は価格帯で言うと10万円~50万円ほどとお値段は張りますが、 そのデザイン性の高さと耐久性を考えると、店舗の家具におすすめです。 安価な椅子を何度か買い替えるより、これらの方が劣化せず使用できるならば ある時点でお得になることもあるかもしれません。 他にもまだまだ様々なデザイナーズチェアがありますので お店にぴったりの一脚を探してみて下さいね。
-
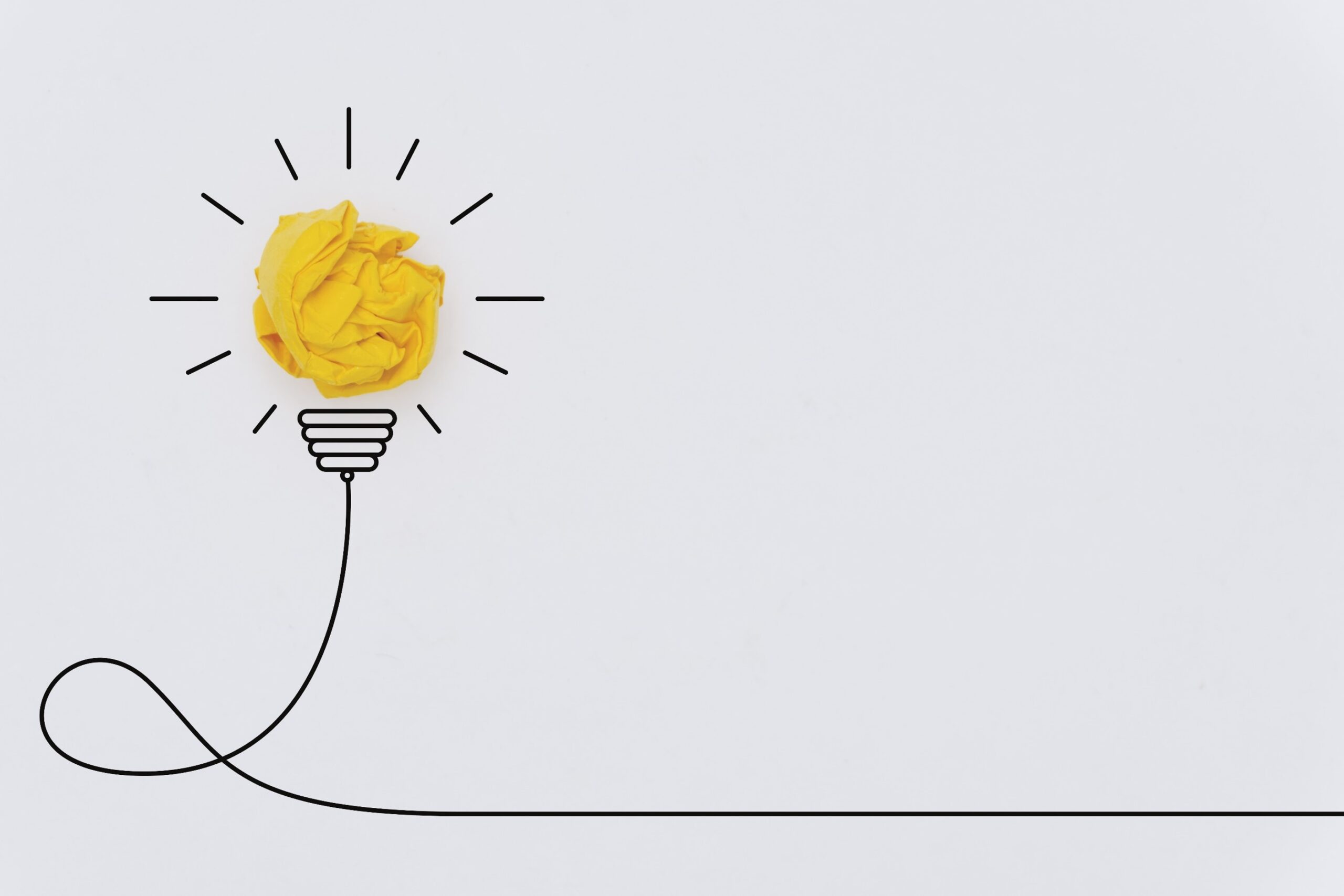
デザイナーズ照明を取り入れよう【店舗の開業なら塊】
デザイナーズ〇〇 こんにちは。 株式会社塊です。 デザイナーズ〇〇。なんだか憧れる響きですよね。 よく聞くのはデザイナーズ住宅でしょうか。 こちらは建築家やデザイナーが監修・設計などを手掛けたデザイン性の高い住宅のことをいいます。 他にはデザイナーズチェアなども聞いたことがあるかもしれません。 こちらも文字そのまま、デザイナーや著名な家具師などが手掛けたオシャレな椅子のことですね。 さて、そんなデザイナー〇〇ですが、照明にもあります。 デザイン性が大変高い照明になりますので、 一つ取り入れるだけで随分と雰囲気を変えることが出来ます。 ですから、新規開店時に設置するだけでなく、 リノベーションや改築・改修時にもおすすめです。 では、どのようなデザイン照明があるのでしょうか? 代表的なものを見てみましょう。 代表的なデザイナー照明 ●イサム・ノグチの「AKARI」シリーズ イサム・ノグチは日本人の父、アメリカ人の母との間に生まれました。 この「AKARI」シリーズは、和紙と竹ひごで作られています。 もともとノグチ氏が岐阜提灯と出会ったことがきっかけでデザインされるようになりました。 「光の彫刻」であると表現されるこのAKARIシリーズは、 和洋室どんな空間にも合うモダンなデザインになっています。 ●ポール・ヘニングセンの「アーティチョーク」 ポール・ヘニングセンによって1958年にデザインされたこの「アーティーチョーク」は その名の通り野菜のアーティーチョークをもとにデザインされた照明です。 絶妙に弧を描く72枚の羽根によって形作られています。 華やかな印象かつ、すっきりとしたデザインです。 ●ポール・クリスチャンセンの「レ・クリント」 デンマーク人のポール・クリスチャンセンによってデザインされた、この「レ・クリント」は 1枚のプラスチックシートを大変複雑で数学的なカーブで折られて作られています。 この折りにより、ランプシェードが美しく独特な彫刻的フォルムになっています。 光と影の優しく繊細なコントラストが魅力です。 ●アルバ・アアルトの「ゴールデンベル」 アルバ・アアルトによってデザインされたこの「ゴールデンベル」は フィンランドのヘルシンキ中心街にある 老舗レストラン「Ravintola Savoy(ラヴィントラ・サヴォイ)」のためにデザインしたものです。 レストランのためにデザインされたものとあって、飲食店にはピッタリです。 ゴールデンベルの名のごとく鐘のような滑らかなラインが美しいです。 一つ一つの大きさはそこまでありませんが、 一つだけでも存在感があります。 無塗装の真鍮で作られたのが最初ですが、 現在販売されている復刻版では違う素材でできたものもあります。 まとめ いかがでしたか。 これだけでなく、まだまだ有名なデザイナーズ照明があります。 どれも特徴的なデザインがあり、それぞれの良さがあります。 一つ取り入れるだけでも大きく雰囲気を変えることが出来るので、 お店に合ったデザイナーズ照明を是非取り入れてみて下さいね。


