BLOG
ブログ
-

自分で図面を作成してもいい?【店舗の開業なら塊】
そもそも「図面」とは? こんにちは。 株式会社塊です。 今日は店舗の施工に欠かせない「図面」の話です。 「図面」と一口に言ってもさまざまで、大きく分けて3つに分かれます。 ①意匠図 意匠図の中には平面図や立面図、断面図、展開図などがあります。 建物の見た目やデザインに関するものがこの意匠図にあたります。 3Dで示された立面図は、かなり完成形に近い図面なので、 これを見れば完成したお店の想像が容易にできます。 ②構造図 構造図の中には床梁伏図、軸組図が含まれます。 構造を形成する柱や壁、床などの部材についての配置や施工手順が示された図面です。 内装というよりは、建物そのもののつくりに関わる図面です。 ③設備図 設備図には電気設備図、空調換気設備図などがあります。 建物の設備系統の施工指示図面になります。 どのような場所にどの数量、どのような設備を設置するのかが書かれています。 図面は細分化していくとその種類はなんと数十にも及ぶのです! 例えば、先日弊社が施工した名古屋市内の居酒屋新設図面は46枚ありました。 もちろん規模や設備、業種などによって異なりますが、 大体~50枚くらいは図面が必要になってきます。 そこまで細かく図面で定めなければ1つのお店は作れないのです。 これを自分で行うというのは無理がありますよね。 しっかりと建築基準を満たすためにも、専門の先生に依頼しましょう。 意匠図は自分で書いてもいい? 特に構造図や設備図は、図面を書くのに専門的な知識を要します。 施工に必要な図面の情報を間違えて書いてしまうと、 施工不良が起こる場合があります。最悪の場合事故に繋がりかねません。 しかし、意匠図に関してはこの限りではありません。 意匠図の中でも例えば、建物の断面図や立面図、展開図になるととても書くのが難しいですし、 専用のソフトなどが必要になってきます。 配置図も建物の高低差や方位、道路との関係を記さなければいけないため難易度が高いです。 しかし、簡易的な平面図ならば作成が可能です。 「JWW CAD」という図面作成の無料アプリがあります。 これは誰でも無料で使用することができ、簡単に平面図を書くことが出来ます。 例えば先日このような意匠図を書いてみました。 なにがなんだか分からない気もしますが…笑 これは新しい事業の作業スペースや販売スペースを簡単に示したものになります。 おおよそこの位置に作業スペースを置いて、 販売物・展示物をこのあたりに設置しよう、商談スペースは2セットをここに など大体の間取りを想像することは可能ですよね。 冷蔵庫やクーラー、照明の位置まで考えると、かなり 具体的に店内予想図が見えてくるのではないでしょうか。 このように意匠図というのは素人の私たちでも描くことができます。 これは施工をする人や図面を描く人にもぜひ共有しておきましょう。 共有することによって、自分の持つお店の理想図をより分かりやすい形で伝えることが出来ます。 なかなか言葉で間取りや完成イメージを伝えるのは難しいですが、 このように図面に表すことによって、高いレベルでイメージをすり合わせることが出来ます。 なんと言っても完成図を具体的に想像することが出来るので、気持ちが高まりますよね! 時間が許すなら、ぜひチャレンジしてみて下さいね。
-

愛知県に食中毒警報が!【店舗の開業なら塊】
食中毒警報とは? こんにちは。 株式会社塊です。 7月3日に愛知県で「食中毒警報」が発令されました。 その名の通り食中毒が発生しやすい状況なので気を付けましょうという警報ですが、 この警報が発令されるには一定の条件があります。 以下、名古屋市のHPから引用しました。 ▼食中毒警報は次の条件のときに発令されます。 なお、発令時から48時間継続し、その後は自動的に解除されます。 第1項 気温30℃以上が10時間以上継続したとき、又はそれが予想されるとき 第2項 湿度90%以上が24時間以上継続したとき、又はそれが予想されるとき 第3項 24時間以内に急激に気温が上昇して、その差が10℃以上のとき、又はそれが予想されるとき 第4項 次の3つの条件が同時に発生したとき、またはそれが予想されるとき 一昨年は2回発令され、昨年は4回ほど発令されました。 異常気象とも呼べるべきこの近年の夏の暑さと日本の湿度の高さは 食中毒を引き起こす恰好の条件となってしまっています。 このように夏に特に増える食中毒。 食中毒警報が発令されるのも例年6月~8月の夏季期間です。 今後も危険となる気候が予想されるので、生鮮食品を扱う飲食店中心に充分な注意が必要になります。 食中毒を防ぐためには では、食中毒を防ぐためにはどのようなことに気を付けたらよいのでしょうか。 まずは、万が一お客さんに食中毒が出てしまったときの対策として、 生産物賠償責任保険(PL保険)に事前加入しておくことが大切です。 飲食業向けの総合保険に付帯されている可能性もありますので、 まずは加入している保険をチェックしてみて下さい。 これから保険加入を考えている方は、このPL保険への加入をおすすめします。 次に、飲食店店内で気を付けるべき点をご紹介します。 ●生ものの提供を出来るだけ避け、充分に加熱する ●調理の前やお手洗い後などには石鹸でよく手を洗い、消毒する ●冷蔵庫の温度は10℃以下にして、食品を詰めすぎない ●食器やまな板、調理器具は十分に洗浄、消毒する ●新鮮な食材を使用する 食中毒は最悪の場合人を死に至らしめる病気です。 いくら大事には至らなかったり、保険に加入して金銭的な負担がなかったりしても、 お店の評判や営業にも影響は少なからずあるでしょう。 夏場、特に食中毒警報が発令されているときなどは 十分に衛生管理に気を配り、それを従業員にも徹底させてください。 本格的な夏の到来はまだまだこれからです。 しっかり対策を行って、防げるリスクはしっかりと防ぎましょう。
-

2024年も半分過ぎました【店舗の開業なら塊】
(株)塊は3期目を迎えます こんにちは。 株式会社塊です。 今日は6月30日。2024年も半分が経過しましたね。 年々月日が過ぎ去るのが短く感じるのは、目新しさが減るからだそうですが 皆さんの半年間はいかがでしたか。 弊社は本日で第2期を終え、明日から3期目を迎えます。 2022年(令和4年)11月1日にスタートした株式会社塊。 わたしたちは電気工事業を母体に総合建築業を営み、 数多くの飲食店、美容院、ジム、事務所、エステサロンなどの店舗から 住宅、大型商業施設や大型倉庫などにいたるまで施工してまいりました。 これはお客様のおかげであること、そして従業員皆が力を合わせてきたからであると思っております。 建設業界がいま苦境に立たされているというのをご存じでしょうか。 もともと汚い、くさい、キツイ、重労働、パワハラ、長時間労働という 悪いイメージが先行している建設業ですが、 それらを改善するべく法改正がなされ、それぞれの企業が努力を重ねているにも関わらず 人手不足は解消されません。 専門的な知識を要するため、人材育成に時間がかかってしまうことも理由の一つではありますが、 やはり常態化してしまっている長時間労働やパワハラなどが大きな原因であると言えるでしょう。 そんな現状を変えるべく、弊社では長時間労働の廃止を掲げ、 パワハラなどがないのはもちろん、社内の風通しを良くして発言のしやすい環境作りを行い 会社や道具、車内の清掃を進めるなどなるべく働きやすい環境にすべく尽力しています。 代表メッセージに目を通してもらうと分かるように、 「遊びのための仕事」という思いが代表にはあり、従来の建設業とは少し異なるような 現代のニーズに沿った働き方の提案をしております。 まだまだ達成できていないところもあるのですが、 今後も社員一同邁進してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 新たなプロジェクトが始動します! そんな第3期を迎えるにあたって、皆様へ報告があります。 弊社は電気工事業・総合建築業のほかに新事業を設立いたします ある時はお化け屋敷であったり、グランピング施設であったり、 様々な新規事業をこの2年考えてきましたが、どれもピンとこず…。 そんな中ある出会いがあり、トントン拍子に話が進んでいった事業があります。 こちら来年から本格始動予定で、今年中には皆様にお知らせできると思います。 今までやってきた建設・建築の知識を役立てつつ、 建設業を通して知り合った協力会社様の協力を得つつ、 素敵な製品を皆さんにお届けできると自負しております! もともと私も話を聞いたとき、その存在を知りませんでした。 しかし、実際に写真を見せてもらうととても素敵だったので、なぜこれが普及していないのか? 知名度がここまで低いのか?と不思議になるほどでした。 ぜひ楽しみにお待ちくださいね!
-

飲食店営業許可を取得するには【店舗の開業なら塊】
愛知県で飲食店営業許可を得るには こんにちは。 株式会社塊です。 飲食店を開業するには、保健所へ営業許可申請をすることが必要になります。 これは各自治体によって内容が異なるので、開業前にしっかりと確認しておきましょう。 今回は、弊社が本社を置く愛知県における営業許可申請の内容を、抜粋して紹介します。 是非参考にしてみて下さいね。 ①厨房と客席が分かれていること 厨房と客席を壁やドア、扉など間仕切りで分ける必要があります。 これは公衆衛生上の危害発生を防止するためです。 お客さんが自由に厨房に出入りすることがないよう、工夫しましょう。 ②内装の素材は清掃、洗浄、消毒が出来る素材であること 床面、内壁、及び天井は掃除が簡単にできるような素材でなければなりません。 特に、厨房の床・壁(床面から容易に汚染される高さまで)においては カーペット素材など不浸透性の材質は認められていません。 また、排水が良好であることも必須です。 ③水道設備は最低3つ以上設置すること 手洗い用の設備、食器洗い用のシンク、食材洗浄用のシンク の3つが最低でも必要になります。 手洗い用の水道設備は、従業員用とお客様用の2つを必要とする店舗が殆どだと思いますので 4つは必要になるでしょうか。 厨房に設置する食器洗浄用シンクと食材洗浄用シンクはそれぞれ用意しなければなりません。 また、用途に合わせて、熱湯や蒸気が供給できるような機能を備えましょう。 二層式シンクならば、一つのシンクで二つの槽に分かれているので、スペースの節約になります。 食洗器と一層式シンクでも許可が下りる場合があるので、 それは事前に確認してみると良いでしょう。 ④冷蔵庫や冷凍庫の設置をすること 食品や加工品を衛生的に保管管理するために、必要な機能を備えた冷蔵・冷凍設備が必要です。 また、これらには温度計を設置していなければなりません。 食品保存・管理にあたっては、それぞれ法律によって定められた規格・基準があるので、 それを参考にしながら必要な設備を揃えましょう。 ➄害獣・害虫駆除の設備を備えること ネズミなどの害獣や害虫の侵入を防ぐ設備と 侵入してしまった際に駆除するための設備を用意しなければなりません。 隙間などは出来るだけ埋めて、殺虫スプレーやネズミ捕りなどの駆除用品を備えましょう。 当たり前ですが、使用する食材などとは別の場所に保管してくださいね。 ⑥更衣室を設けること 従業員数に応じた十分な広さのある更衣室を設ける必要性があります。 またこれは作業場への出入りが容易な位置に設置しなければなりません。 店外などに設けるのはよくないということですね。 お客様からもあまり見えない位置に設置する方がベターでしょう。 まとめ 上記は共通基準の一部で、これらのほかに業種によって個別の基準が設定されているので こちらも併せて確認するようにしてください。 施設基準は、開業前どころか内装施工前に知っておくべき内容です。 しっかりと理解したうえで、基準を満たす飲食店をつくってくださいね。
-
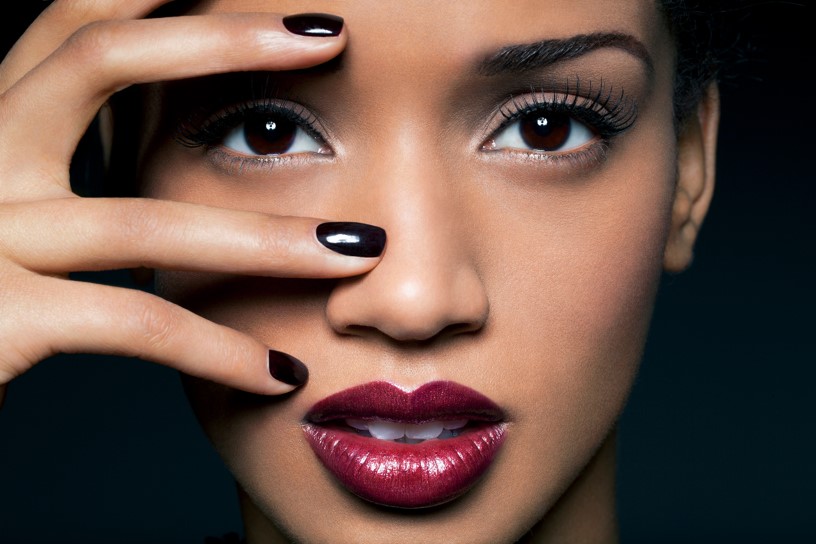
ネイル美容への注目度の高さ【店舗の開業なら塊】
ネイル美容の需要は? こんにちは。 株式会社塊です。 弊社には今3名の女性スタッフが居ます。 そのうちネイルをしているのはなんと3/3! 全員がジェルネイルをしています。 そのうちの1人はネイルサロンで施術してもらうのではなく、なんと自分でジェルネイルをしているそうです。 爪は常に目に入るので、特に女性にとっては綺麗に整えておきたいパーツです。 では実際、女性はどのくらいネイルをしているのでしょうか。 株式会社しんげんが行った市場調査によると、過去1年以内のネイルサロンの利用率は26.5%で セルフネイル実施者はなんと75%にも及びます。(複数回答可能) そして1年間でネイルを全くしなかったという人はわずか9.5%しかいないのです。 女性のネイルへの注目度の高さがうかがえますね。 セルフネイル用品が充実し、安価で高品質な製品が手に入るようになったことも ネイル人口が増えた要因の一つになっています。 また、マニキュアをしている人は57.5%で、ジェルネイルをしている人は47%のようです。 以前はセルフネイルと言えばマニキュアが主要でしたが、このデータからも分かるように、 ネイルサロンに行くことなく、弊社社員のようにセルフでジェルネイルを行うという層も増えているようです。 個人的には、ジェルネイルの需要がここまでマニュキュアと拮抗しているとは思いませんでした! ネイルサロンだとそれなりにお金がかかりますし、 ジェルネイルをセルフでやるのは技術的に難しく、時間もかかるのですが それでもジェルネイルの需要がかなり高くあるということですね。 20代以上の女性全体の約9割が行うというネイル。 直近のコロナ禍により外出自粛のムードが蔓延し、一時期は業界全体が不振だったようですが やはり依然としてその需要は高そうです。 今後は外向き需要が大きくなっていくはずなので、さらなる成長が見込めますね。 ネイルサロン開業で成功するには ネイルサロンの開業方法は少し前に紹介していますので、そちらを参考にしてみてください。 今日は、開業後にどのようにして成功するかということにフォーカスして話したいと思います。 Beauty総研によると、ネイルサロンでの1回あたり利用金額は5,872円が平均だそうです。 多くの人が行うメニューは「ジェルネイルオフ+新しいジェルネイル」なので、 大体これくらいの金額でしょう。私も大体これくらいです。 店舗開業における利益の上げ方は大きく分けて2つです。 (1)売り上げを上げる=集客数を増やす/単価を上げる (2)利益率を上げる どちらかしかありません。 まず(1)売り上げを上げる方法を考えましょう。 これは上記にもあるように、お客さんの数を増やすか、単価を上げるかしかありません。 お客さんの数を増やすためには、マーケティングが大事になっていきます。 SNSやチラシ広告、インターネット広告などを駆使してとにかく認知してもらいましょう。 予約も、電話予約だけでなく口コミサイトやLINEなど様々な導線を用意すると良いです。 キャンペーンなどを行って、集客を促したりするのも手です。 次に、単価を上げるには、営業または技術力の向上が必要になってきます。 例えばあなたがネイルに関する何かに特化した技術を取得したなら(コンテストに優勝、芸能人への施術経験、キャラクターネイルに特化など) それによりメニュー単価を上げても集客が可能でしょう。 ネイルは特別な日のみにするという人も多いので、そこの需要と提供サービスがマッチすれば 価格が高くてもお客さんはつくはずです。 技術取得以外で単価を上げようと思うと、営業が必要になります。 例えば、シンプルなネイルに比べて、パーツを付けたネイルやデザインネイルは価格が高くなります。 押しつけがましい営業にならない程度に、 パーツを付けたネイルやデザインネイルの提案をするのがいいでしょう。 実際のサンプルデザインをお客さんの近くに飾るのも効果が得られます。 では(2)利益率を上げる方法を考えます。 例えば売上100万円で現在の利益率が20%だとすると、利益は20万円ですね。 しかし、これを売り上げ(客数・単価)はそのままに利益率を35%に上げるとどうでしょうか。 客数も単価も上げずに利益を15万円も多く得ることが出来ます。 実際はこのように単純には利益率を上げるというのは難しいですが、 きちんと見直すことによって、意外なほど利益率を上げることができます。 同じ売り上げで利益率を上げるためには、とにかく支出を減らすことです。 いまどのような支出があるでしょうか。 「人件費」「水道・光熱費」「ネイル材料費」「備品費」 大体このあたりでしょうか。 いったんネイルサロンを開業したら、ネイルの種類をそこまで増やす必要はなくなります。 なので、ネイル材料費や備品費はそこまで考えなくていいでしょう。 考えるべきは人件費と水道・光熱費です。 水道光熱費の節約方法としては、 お客さんのいない時間は消灯する、トイレはセンサー式照明にする、 照明を蛍光灯からLEDに変える、冷暖房は弱めに設定する(毛布や扇風機を用意) 冷暖房機器の掃除をこまめに行う、などが考えらえます。 小さなことですが、一つ一つやっていくと結構大きな違いになりますよ。 人件費で言うと、まず人を雇うときに本当にスタッフが必要なのかを考えて下さい。 客数や売り上げとスタッフの人数が合っていないようであれば、 募集をかけるべきではありません。 また、客数の少ない平日昼間はスタッフ数を少なくするなど、 シフトの工夫もしましょう。 時給や勤務形態などもしっかり管理しながら、人件費について考えて下さいね。 まとめ いかがでしたか。 ネイルサロンにおいては、飲食店のように在庫の廃棄が出るわけではなく、 水道・光熱費もさしてかからないので、 支出を抑えることによって利益率を上げようと考えるのはなかなか難しいです。 広告宣伝に力を入れて集客を頑張りながら、単価を上げるというのがいいでしょう。 開業が容易なだけあって競合店が多いため、なかなか成功が大変かもしれませんが 一つずつこなせば必ず結果はついてきます。 成功できるように、日々の見直しから頑張っていきましょう!
-

賞味期限管理のデジタル化は必要か【店舗の開業なら塊】
店舗業務におけるデジタル化の状況 こんにちは。 株式会社塊です。 ここ数年にかけて、世界的にデジタル化がものすごいスピードで推し進められています。 インターネットが普及し、スマートフォンが登場するまでには時間がかかりましたが、 それ以降は目にも止まらない速さで進歩しています。 いまや私たちはデジタルの恩恵なしでは暮らしていけなくなりました。 デジタル情報によって導き出された天気予報を参考に衣服を決め、 その衣服や手に持っている傘の製作にはデジタル技術が用いられ、 デジタル制御された車に乗り、SNSで連絡を取り、電子マネーでお金を払います。 このように身の回りにはさまざまな「デジタル」があふれているのですが、 こと「仕事」に関してはあまりデジタル化が進んでいないように見受けられます。 とくに小売業、飲食業ではそれが顕著ではないでしょうか。 人と人が関わる「店舗営業」である以上、仕方がない部分もありますが、 なぜ、このようになかなかデジタル化が進んでいかないのでしょうか。 その実態と、デジタル化によるメリットデメリットはどのようなものがあるのでしょう。 株式会社シムトップスが小売業を対象に、 賞味期限の管理について調査したデータがあるので参考にして考察してみたいと思います。 進まないデジタル化、デメリットとメリットは まず、同社は賞味期限確認の頻度を尋ねました。 賞味期限チェックは68.5%が毎日行うと回答し、次点が1週間に1回の頻度で10.2%。 圧倒的に毎日チェックするというお店が多いようです。 毎日多くの商品の賞味期限をチェックしなければならないことを思うと、 これはかなりの苦労になることが想像に難くないです。 では、それら賞味期限の管理を何で行っているかというと、 1位が紙帳票で26.9%、2位が在庫管理システムで22.2%でした。 Excelやスプレッドシート管理と回答した人も8.3%おり、 やはりまだまだデジタル化が進んでいないことが分かります。 従業員の約40%が現行の賞味期限確認方法には満足できておらず、改善が必要であると考えらえます。 そんな中、デジタル化を進めていない店舗の半数近くがデジタル化を考えてはいるようですが、 依然それは半数止まり。 店舗業務をデジタル化することのメリットやデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。 メリット ①チェック漏れやミスのリスクが減る 人の目と手なので、やはりミスは生じます。 時間のないとき、業務に追われているときは チェックがおろそかになると回答している人がいたり、 品数や種類が多く見落としてしまうという回答をしている人がいました。 このような人為的なミスは、デジタル化によってなくすことができます。 ②時間や人件費を節約できる 慢性的な人手不足はどの業種にも言える問題です。 もちろん小売店もこの限りではありません。 毎日チェックしなければならない賞味期限管理業務をデジタル化することで、 時間と人の節約になりますよね。 ③在庫破棄リスクが減る デジタルで在庫を一元管理することにより、 人の手による管理不足によって生じる、過剰在庫や廃棄ロスのリスクを減らすことが出来ます。 デメリット ①導入に費用がかかる デジタル化を進めるにあたって、プランなどにもよりますが、 モバイル端末代金やシステム構築費用などが必要になります。 大企業ならば支店それぞれに導入しなければならないため、 かなりの導入費がかかることを覚悟しなければなりません。 ②データ入力の誤りが頻発し、精度が担保できない デジタル管理とはいえ、その数字データを打ち込むのは人間だったりします。 「60」のところを「600」と入力していたら大変なことになります。 手書きだとこういったミスは起こりにくいので、 このあたりはデジタル化において気を付けなければいけない点ですね。 ③データ更新が遅れると、最新の情報を確認できない 例えばExcelのデータなどで共有していれば、最新データのタイムラグは皆無です。 誰かが入力して保存さえしていれば、即時反映され、常に最新データの状態です。 紙帳票も同じです、離れている店舗のデータも写真化して送るなど対応が出来ます。 しかし、デジタル管理だと、 そのデジタル管理システムを提供しているサーバーの状態によって、データが左右されることがあります。 サーバーに不具合が生じれば、入力したものの反映が即時されないということも起こってしまうのです。 以前、某大手銀行のシステムがダウンし、入出金できないということが起こりましたよね。 これがデジタルの怖さで、場合によっては損失を被ることもあります。 ④システムが複雑で担当者の教育が必要 どのようなシステムをどの程度使用するかにもよりますが、 様々な業務管理のデジタル化を進めれば進めるほど煩雑になります。 特にデジタルネイティブ世代でない人たちにデジタル管理を任せようと思うと 相当の教育が必要になります。 教育担当の人件費に、教育の時間、それらも考慮しなければなりません。 まとめ いかがでしたか? こうしてみてみると、デジタル化にもまだまだ課題は残り、 一概にDX化を進めるべきだということは難しいかもしれません。 人件費や時間と折り合いを付けながら、ぜひ自分のお店にとって最適な方法を選んでくださいね。


