BLOG
ブログ
-

移転・拡大時の懸念【店舗の開業なら塊】
移転・拡大、喜ばしいことですが… こんにちは。 株式会社塊です。 「事務所を移転しようと思っていて…」 「2店舗目を出そうと思っています」 事務所やお店の移転・拡大は喜ばしいことですよね! 聞いているこちらも嬉しい気持ちになります。 かく言う弊社も実は2月に事務所を移転します。 12月から着工し、2月には完全移行を予定しています。 なんと次の事務所は今の4~5倍ほどの大きさがあります! 場所は瑞穂区になります。 お近くの方は是非お立ち寄りください。 また詳細等お知らせできたらと思います。 事務所移転は急務だったのですが、6月頃から探しはじめ、先月漸く移転先が決まりました。 物件との出会いは本当にタイミングや運としか言いようがないのですが、 それゆえ難航することが多いです。 どれだけネットを見漁り、何件の物件に問い合わせ、内見に行ったことでしょうか。。。 結局は協力会社の方の紹介で移転先の物件が決まりました。 どれだけ余力があり移転・拡大しようと思っても、 それに見合った物件がないと実現できません。 株式会社シンクロ・フードの調査によると、 店舗出店時の悩みの第1位はやはり「物件探し」で67.7%となっています。 次いで「厨房・内装工事(44.3%)」、「開業・運営資金の調達(39.4%)」と続きます。 物件探しは最低半年以上前から行いましょう。 予算、立地条件、大きさ、形態などを事前に決めて探します。 そして良さそうな物件があったら、契約条件や残置物などの確認をしっかり行いましょう。 事業用物件、どのように探す? 事業用物件を探すのにはどのような方法があるのでしょうか。 ①オンライン不動産サイト いわゆるアットホームやホームメイト、goo不動産などのオンラインサイトで探す方法です。 一番手軽に探すことが出来ます。 しかし、オンラインに掲載時には魅力ある物件は借り手が既に決まっていることが多いです。 さらに膨大な数から探すのは中々骨の折れる作業ではあります。 しかし、常にチェックすることで思いがけず良い物件と出会えることもあるでしょう。 ②不動産仲介業者 店舗を構えている不動産仲介業者の元へ直接訪れ探してもらいます。 出来れば移転地域のその場所に根差した不動産業者だと尚良いです。 物件数も豊富で、交渉などで融通が利く場合があるからです。 何度か通ったり、お客さんを紹介したりなど関係性を濃くすることで 優先的に物件を紹介してくれるようになりますので意識してみて下さい。 ③紹介など 例えば、先日お会いした飲食店のオーナーさんは 通っていたお店のオーナーが店仕舞いをすることを聞き、 そのまま居抜きで借りることを交渉したそうです。 弊社の新事務所も上記にあるように結局は紹介で決まりました。 決定前は①のオンラインサイトをメインに探していましたが、 様々な協力会社さんに「移転考えてないですか?」と聞いたり、 「周りで倒産した会社ないですか?」と聞いたり…。 このような横のつながりやネットワークで物件が見つかることも結構あります。 常にアンテナを張っておくと良いでしょう。 出来れば、①②③すべて並行して行えると良いです。 肌感では、そうしてようやく半年くらいで見つかるかどうかという感じです。 店舗や事務所の移転・拡大などの準備は今現在の仕事を続けながら行わなければなりません。 新規開業とはまた別の忙しさ・大変さがあるので、早め早めに準備に取り掛かりましょう。 その準備の中でも大変な「物件決め」 難航するがゆえに移転や拡大を諦めてしまう方も多くいます。 そうなってしまわないよう、様々な方法を駆使しながら時間をかけて物件選定を行いましょう。
-

色のもたらす効果【店舗の開業なら塊】
今日のあなたの服の色は? こんにちは。 株式会社塊です。 10月に入りました、いよいよ本格的な秋が始まってもおかしくないですが 名古屋はまだまだ暑い日が続きますね…。 さて、今朝は久しぶりに電車通勤だったのですが、 私を含めおおよそ8割の人が半袖をまだ着ていました。 しかし、色味がベージュだったり茶色だったり、オレンジや緑だったりと どことなく秋冬を意識した色味のように感じました。 まだ暑いですが、なんとなくサンダルはもう履きづらかったり、 原色のカラーは控えるようにしたり、 季節の訪れをどことなく感じている人も多いようです。 そんな今日この頃ですが、皆さんは何色のお洋服をチョイスしたのでしょうか。 私はというと、ショッキングピンクを選びました(!) 上記の話とは逆行するような選択なのですが、これを選んだのには理由があって、 昨晩は睡眠時間が短く、本日は曇りでどんより、 むしむしとした天気なため気分がどうしても優れなかったのです。 なんとか元気を振り絞るために、色の力を借りることにしました。 本当に不思議なもので、明るい色の服を着ているとなんとなく元気が出てくるし ピンクに合わせてリップも明るいピンクにしようかなと前向きな気持ちが生まれます。 青空の抜けるような青をみたらすがすがしく感じたり、 夕焼けのオレンジ色を見たらなんとなく寂しく感じたり、 森の緑に包まれたらリラックスしたりと色が人間にもたらす効果は大きいです。 さて、店舗の内装や看板、ユニフォームなどのデザイン・色はもう考えていますでしょうか。 折角なので、色の力を借りて、より美味しそうなお店に見せたり 入店しやすい雰囲気をつくったりしてみませんか。 色による効果 アメリカ元大統領のドナルド・トランプ氏は常に赤色のネクタイを身に着けています。 これはジョンFケネディ氏もそうでした。 赤色がアメリカ国旗に使われているため好んだとも言われていますが、 本当の理由は赤色のもつパワーにあるのではないかと考えられます。 赤色ははっきりとした力強い色です。 赤色から連想されるのは太陽や火、血、怒り、情熱などがありますが いずれも苛烈なイメージがあります。 そんな赤色にはそれを身に着けている人を力強く見せたり、 発言に信憑性をもたらしたりします。 色の効果は着用している本人はもちろん、それを見る相手にも作用するのです。 そんな赤色のパワーを上手く使っていたのがこの2人なのではないでしょうか。 また、赤色は食欲を引き出す色とも言われています。 マクドナルド、ケンタッキー、一蘭などいずれもロゴや看板に赤色をメインに用いています。 これはそのような赤色のパワーを上手く活用していると言えるでしょう。 ここで、それぞれの色がもたらす意味を以下に紹介します。 赤:エネルギー、強さ 青:冷静、知的 緑:健康、自然、安全 ピンク:愛情、優しさ 黄:活発、明快 オレンジ:陽気、親しみ 紫:高貴、優雅、ミステリアス 白:潔白、純粋、平和 黒:重厚、高級 聞いたら、なんとなく感覚的に分かるという方も多いのではないでしょうか。 そんな色が持つ意味やパワーを活用してお店のロゴや看板、内装に用いることで コンセプトにより沿ったお店をつくることが出来ます。 ある焼肉屋さんの話です。 名古屋市の郊外にあるその焼肉屋さんは、集客にお困りでした。 しかし、看板を白地に黒文字から赤地に黒文字に変え、 牛のデフォルメキャラクターを載せたらどうでしょう。 売上高前月比150%、新規のお客さんも増えたようです。 このように視覚から得る効果は大きいので、 ぜひ上手く活用してみて下さい。
-
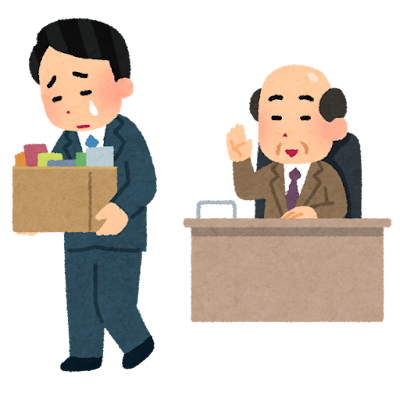
従業員を解雇するときには【店舗の開業なら塊】
アルバイトってどんな立ち位置? こんにちは。 株式会社塊です。 飲食店なり小売店なり…店舗の経営には人が必要になってくる場合が多いです。 いくらキャパシティの狭い飲食店でも、料理を作る人と提供する人の2人は欲しいところです。 小売店は小規模で行う場合は1人でも回せるかもしれませんが、 経理やレジ、接客、棚卸、発注、マーケティングなど全てを自分で行うのはやはり大変です。 どのようなお店も人手が欲しい、アルバイトを雇いたいと考えるでしょう。 しかし、いざアルバイトを募集して人を雇ったはいいものの、 その人が人間的に問題のある人であった… 勤務して欲しい時間に勤務してくれない… 当日連絡もなしに来なかったりする… など問題を抱えているという話をよく聞きます。 アルバイトは一般的に 「主に学生やフリーターなどの若者が、一時的な収入を得るために空き時間を利用して働くこと」 と定義されています。 アルバイターは、福利厚生などによって企業やお店から守られることがありません。 ですから負うべき責任はありませんし、事実負わせるべきではありません。 お店側の心情としては、お店の一員として働く以上ある程度の仕事を期待するでしょう。 しかし、業務内容や出来ではなく労働時間に対してお金を支払っている以上、 過度な期待をするのはお門違いというものです。 もちろんそれは理解しているが、それにしても酷い勤務態度の人が多いというのです。 面接時に数十分顔を合わせた程度の人なので、見誤ることはあるでしょう。 しかし、いったん雇ってしまうと簡単に解雇という訳にはいきません。 では、実際に店舗に不利益を被るような人を雇ってしまった場合、 どのように対処すればよいのでしょうか。 「解雇」の難しさ いったん人を雇ってしまうと、その後に「やっぱやめた」 ということはまかり通りません。 労働者にも権利があり、それは守られなくてはならないからです。 しかし、だからといって働かない人を善意で雇い続けろという訳ではありません。 経営者には経営者の権利があります。 そんなお互いの権利がどこまで認められるかという規定をした法律が 「労働基準法」いわゆる「労基法」と呼ばれるものです。 労基法によると、解雇については以下のように記されています。 ────────────────────────────────────────────── 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ────────────────────────────────────────────── 一言で言うと、解雇は30日前に告知しましょう、ということです。 しかし、事前告知さえすればどんな理由であっても辞めさせられるかというとそうではありません。 解雇にはそれ相当の理由が必要で、その詳細については就業規則で定める必要があります。 解雇理由が不明確である場合それは不当解雇にあたり、無効になる可能性があり 最悪の場合裁判などに発展することもあります。 労働基準法第89条には 「常時10人以上の従業員を雇用する事業者は就業規則で解雇の事由を定めなければならない」 と記載がありますが、余計なトラブルを避けるために 従業員が10人以下であったとしても就業規則を作成しておく方が良いでしょう。 また、労働契約法においては 「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」 との定めもあるため、やはりどのような事業者も就業規則を作成するのがベターです。 ①就業規則に解雇事由を定める ②30日前に告知する or 解雇予告手当を支払う この条件をクリアし、相当理由がある場合に解雇を行うことが出来ます。 ただし、 ※病気やケガによる休業期間とその後30日間、 また産前産後の休業期間とその後30日間は解雇してはならない。 ※労働基準監督署等への法令違反の通告を理由に解雇してはならない。 という2つの制限があります。 ここは忘れないようにしたいものです。 まとめ 就業規則の解雇事由としてよく見られるのが ●勤務状況の不良●勤務成績の不良●業務に耐えられないとき●労働者としての職責を果たし得ないとき などの記載です。 これを読んでいかがでしょうか。 ”不良”とはどのようなことを指すのか、”職責”とはどこまでのことを言うのか、 結構曖昧に表現されていますよね。 解釈が広いため、ある程度は経営者の裁量で解雇通告が可能ということになります。 しかし、労働者から「不良ではなかった」「職責を果たしていた」と主張された時は少し厄介です。 裁判で争うことになった際にはその”不良”や”職責”の程度が問われることになります。 そのようなことを避けるためには、もう少し具体的に記述するのが良いでしょう。 もし1人でも人を雇うならば、後から後悔しないためにもぜひ就業規則を作成してみてくださいね。
-

10月の範囲拡大前に!いまさら聞けない社会保険【店舗の開業なら塊】
社会保険ってなに? こんにちは。 株式会社塊です。 「10月から社会保険の適用範囲が拡大するよ~~~、 事業者の皆さんは注意してね!」 最近こんなCMが流れるようになりましたね。 令和2年の年金制度改正により、令和6年10月から 従業員数が51人から100人の企業で働く短時間労働者(アルバイト・パートなど) が新たに社会保険の適用対象になります。 従業員数101人~と定められていた制限が引き下げられるということです。 そもそも「社会保険」とは何なのでしょうか? 会社にお勤めの方は毎月当たり前のようにお給料から天引きされているので 意外にそれがなにかを意識していない方も多いのです。 この機会に社会保険とはなにかを今一度確認してみましょう。 「社会保険」とは会社員や公務員など働く人たちが 強制的に加入しなければならない公的な保険制度です。 これは任意ではなく義務なので、一部例外を除いて労働者は必ず加入しなければなりません。 保険者として運営するのは国や公的な機関。 その保険者に対して保険料を支払うのは労働者である私たち従業員と企業です。 そんな社会保険ですが、これは5つの保険の総称を指します。 ①健康保険 企業と従業員が折半して負担します。 業務外で病気やケガをした際に保障される医療保険のことです。 今もお財布に入っているはずです。一番馴染みがあるのではないでしょうか。 ②厚生年金保険 企業と従業員が折半して負担します。 いわゆる年金のことです。65歳になったら支給されます。 20歳以上の全員が加入しなければならない国民年金保険はここに含まれています。 ③介護保険 企業と従業員が折半して負担します。 こちらは40歳以降の加入が義務付けられています。 介護が必要となった際に、介護サービスを受けられる保険です。 ④労災保険 全額企業が負担します。 業務上または通勤時において病気やケガをした際に保障される医療保険のことです。 死亡時には遺族のためにも保険給付を行います。 ➄雇用保険 企業と従業員が負担しますが、企業の方が負担額が大きいです。 失業時などの保障がされる保険です。 この5つの保険をまとめて社会保険とよび、 代表取締役をはじめとした役員、従業員、一部のアルバイトやパート、 働くすべての人が加入します。 法律においては、厚生年金保険法によって規定されています。 10月からの範囲拡大で何が変わる? 冒頭にも記しましたが、来月より社会保険制度の適用範囲が拡大されます。 どのような変更点があるのでしょうか。 お店を経営する方、自分にも関わりのあることかもしれません。 きちんと把握しておきましょう。 現行の制度では、パートやアルバイトは 以下の条件を満たす際に社会保険への加入が義務付けられています。 ① 従業員が101人以上であること② 週の所定労働時間が20時間以上であること③ 所定内賃金が月額8.8万円以上であること④ 2カ月を超える雇用の見込みがあること⑤ 学生ではないこと この①が10月以降以下のようになります。 ① 従業員が101人以上であること①従業員が51人以上であること 社会保険適用者が増えると一番困るのは企業です。 なぜなら企業の社会保険負担額が大きくなるから。 極端な話ですが、 例えば代表者1人とアルバイト50人で回しているお店があったとしましょう。 そのうち30人は上記の②~➄の社会保険加入条件を満たしてるとします。 その場合、今まで社会保険料はその代表者の1人分を支払えばよかったのです。 しかし、来月からは31人分の社会保険料を支払わなければならなくなります。 どれだけ負担額が増えるのでしょうか。考えたくもないほどです。 従業員にしてみても、お給料が社会保険料分天引きされるようになるので、 手取り額はぐっと下がります。 しかし、メリットもあります。 まず、出産手当金や傷病手当金が得られます。 出産や傷病に伴う休業期間中の手当てを受け取ることが出来ます。 さらには、国民年金以外にも厚生年金分の年金を 65歳になった時に受け取ることが出来ます。年金額が増えるということです。 悪いことばかりではありませんが、事業者・従業員ともに理解を得ることは難しそうです。 事業者としては、離職を防ぐために いままでの手取り額と変わらない給与を支給することを考えなければなりませんが、 人件費をいたずらに増やすことになるため中々そうもいきません。 まずは自分が、自分の運営する会社や店が今回の制度変更に該当するのか確認し どのような方針をとるのか決めなければなりません。 方針を決めたら、以下のような計画に沿って行動しましょう。 出典:「社会保険の適用が拡大!従業員数51人以上の企業は要チェック」 まだまだ暑い日が続きますが10月までもう僅か。 早め早めの行動をしていってくださいね。
-
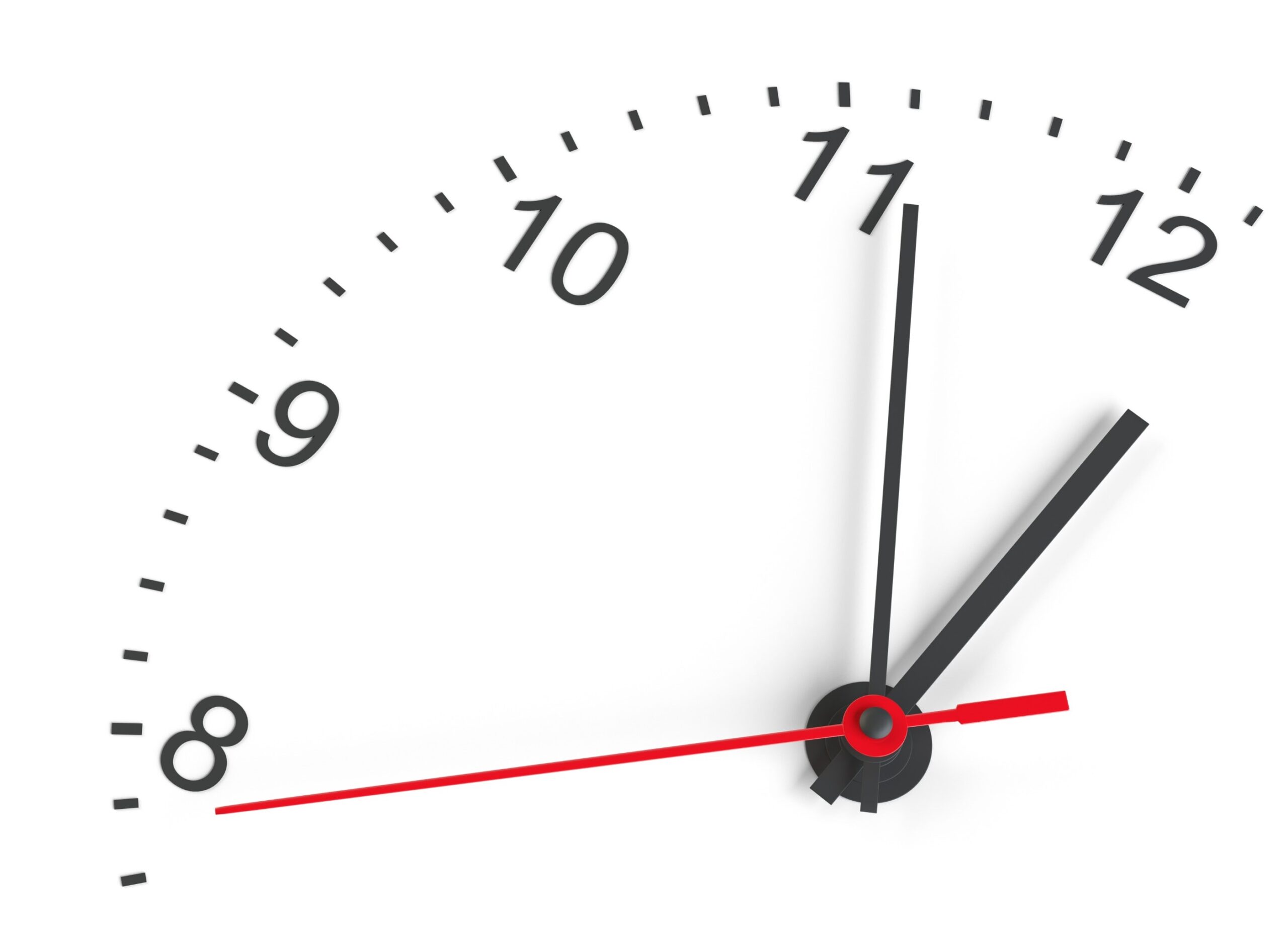
居酒屋がランチ営業する理由【店舗の開業なら塊】
飲食店で営業時間を延ばすということ こんにちは。 株式会社塊です。 先日、栄で打ち合わせを終えた後折角だからランチでも食べようという話になり 皆で天丼のランチをいただきました。 このお店はもともと夜営業のみの天ぷら酒場で、 ランチを始めたのはここ数年だと話していました。 このように、最近では居酒屋やバーなどの夜営業をメインとしている業種が ランチ営業を始めたり、 カフェがお酒などを提供する夜カフェを始めたりと 営業時間を延ばす飲食店が増えているように感じます。 こうして営業時間を拡大することによって、様々なメリットを得られることができます。 しかし、一方でデメリットも少なからず存在します。 一昔前は、無理してでも長時間働くことでお金が多く手に入ると思われていました。 長時間労働は「正」だったのです。 しかし、必ずしもそうではないようです。 営業時間を拡げることは果たして良いことなのでしょうか。 一緒に考えてみましょう。 営業時間を延ばすことのメリットとデメリット メリット ●異なる顧客層にアプローチできる 昼のランチに訪れる層と、夜の居酒屋に訪れる層は異なることがほとんどです。 幅広い層に向けてアプローチが可能になります。 ●売上が上がる 営業時間を延ばせば、その分注文が増えるため単純に売り上げは上がります。 利益が上がるかどうかは一旦おいておきます。 ●リピーターを獲得できる ランチ時の天丼が美味しければ、夜の天ぷらも食べてみたくなります。 お得なお寿司ランチのネタが美味しければ、今度はお酒と一緒に…となります。 ●食材の廃棄を減らせる 焼肉屋さんがランチにお肉がゴロゴロ入ったカレーを提供しており、 それがとても美味しくてお値打ちだったため、お店の方にお話を伺いました。 前日に残ってしまったお肉を廃棄するくらいなら、とカレーにして提供しているようです。 生ものには鮮度が求められるので、どうしても廃棄が出てしまいます。 どうにかその量を減らせないかという苦肉の策であったようですが、 今やランチ時には行列が出来る人気店になったそうです。 デメリット ●利益が下がる 一番のデメリットはここにあります。 労働時間を延ばすことによって必然的に人件費もかかります。 それを上回るほどの売り上げ、利益を出せれば良いのですが、 こればっかりは何とも言えません。 ただ、サブ営業の時間帯に提供するものは利益率が高いものの方が良いでしょう。 ●迷走してしまう 例えばサブ営業が売上高・利益高ともにメイン営業を超えたとします。 それには様々な理由が考えられます。 全く異なる商品を提供していたとしたら、それが理由かもしれませんし、 そもそもその立地は夜より昼の方が集客がしやすのかもしれません。 理由のきちんとした精査が出来、活かすことが出来ればそれはきっとためになるでしょう。 しかし、その精査が曖昧なまま無理に業態転換をしようとしてしまったり、 営業時間を変更してしまったりするのはかえって逆効果です。 もともとのお客さんが離れることにも繋がってしまいます。 ●ライフワークバランスがとれなくなる 仕事のための人生なのか、人生のための仕事なのか ───。 よく言われる言葉です。 日本は諸外国と比べ労働時間が長いと言われます。 長時間労働の常態化を改善するため国を挙げて取り組んでいますが、 現場レベルではなかなか改善されていないというのが現状でしょう。 仕事を終えて後は寝るだけ、休みの日は仕事の疲れを癒すだけ。 そんな方も多いのではないでしょうか。 営業時間を延長することによって、当たり前ですが余暇は短くなります。 ずっと楽しんで店舗経営を続けていくために自分はどのような選択をしたらいいのか ということを考えて欲しいと思います。 まとめ いかがでしたか。 居酒屋がランチを始め、カフェがバーをやりだす。 今以上のことを求めて努力することは素晴らしいですが、 そのメイン営業以外の時間がどのような効果をもたらすのか、 しっかりと考えた上で行ってくださいね。
-

マクドナルドが髪色自由化へ【店舗の開業なら塊】
マクドナルドが髪色に関する制限を撤廃 こんにちは。 株式会社塊です。 皆さんが今お勤めの職場には髪色・服装規定はありますか? 業種にもよりますが、社内規定が厳しいという方も少なくないのではないでしょうか。 弊社は特に規定はありませんが、唯一髪色が「金」は許されていません。 理由としては、お客様に威圧感を与えてしまう可能性があるため。 その他は特に厳しく規定を設けているわけではありませんが 信用・信頼していただくためにはある程度の身だしなみは必要だと考えております。 さて、そんな髪色についての話題です。 日本マクドナルド株式会社が、9月10日付でアルバイトスタッフのアピアランスポリシーを改訂、 髪色を自由化しました。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ■アピアランスポリシー(改訂後、一部抜粋)⚫︎ 清潔感があり、お客様へ不快感を与えないか✔︎ 清潔感のある髪型✔︎ 接客のプロとしてのメイクを心がける⚫︎ フードセーフティに影響がないか✔︎ 装飾品は身につけない✔︎ ひげをきれいにし、もみあげは短く清潔に⚫︎ 多様性を大切にしているか✔︎ NEW!髪色は自由~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 引用元:「アピアランスポリシーを改訂し、店舗で働くクルーの髪色自由化へ約20万人の多様な人材が、さらに自分らしくいきいき働ける環境を目指して」 マクドナルド社は創業当初から「ピープルビジネス」という理念をかかげ、 従業員を大事にしてきました。 今回髪色自由化の実現により、従業員がより自分らしくポジティブに働けるような環境づくりが進むでしょう。 ひいてはそれが、お客様が快適に過ごせるお店作りに繋がるという狙いです。 ポリシー改訂前に試験的に導入した大阪府のマクドナルドでは、以下のような声が聞かれました。 ●「好きな髪色にすることで、より仕事のモチベーションも上がった」 ●「自分らしさを認めてもらえているように感じる」 ●「髪色を問わなくなったことで、より会話が生まれる、活気のある良い職場になった」 さらに、4月のクルー採用人数は前年比で約3倍の30人となり、 安定した店舗運営がかのうになったそうです。 髪色自由化に見る社会需要 日本は、海外に比べて就業時の服装規定が厳しい傾向にあります。 その理由の一つに、日本人の髪色や目の色が黒~茶色に限定されており、 外国人の受け入れもそれほど進んでいないというものがあります。 黒髪はきちんとしている、清潔感があるという印象を与えるため、 飲食店など高い衛生管理が求められるような場ではやはり重宝されます。 しかし、アルバイトのために好きな髪色を我慢しなければならないというのは 昨今の若者にとっては耐え難い苦痛のようです。 Z世代に向けたある調査によると、 アルバイト探しで最も重要な条件は「給与が高い」24% を抑え、 「服装・髪型・ネイルが自由」46% が1位になったそうです。 特に10代からの支持は圧倒的でした。 近年のトレンドとして、若者は給与よりも環境を重視する傾向にあります。 働きやすい、やりがいを感じる、個性が発揮できる、自分らしくいられるなど そういったことが重要になってくるようです。 また、老舗スーパーの「ユニー」では2022年11月に店員の髪やネイルに関する規定を緩めました。 その変更から1年後にはアルバイトの応募数はかつての2倍、過去最高人数となりました。 近年、どの業界でも人材不足が叫ばれています。 建設や運送、物流業の2024年問題という言葉を聞いたことがある方も多いことでしょう。 これはしかし飲食店、小売店などの店舗経営においてもその限りではありません。 どのように人材確保をしていかなければいけないかという課題が急務ななか、 このように服装規定を緩めることによって高い効果が得られることが分かりました。 もちろん「自由」といってもそれは制限された自由であるべきで、 人に恐怖心や威圧感を与えるようなものは認めてはなりませんが、 従業員の自主性を高めるという目的においても、検討の余地はありそうです。


