BLOG
ブログ
-

コバエが一瞬止まった!その料理、大丈夫?【店舗の開業なら塊】
コバエによる人間への健康被害 こんにちは。 株式会社塊です。 最近急に暖かくなりましたね!ここ数日は寒さが残っているようですが…… 桜の開花も宣言され、春本番まであと少しといったところでしょうか。 さて、最近ジョギングコースである川沿いに羽虫が出てくるようになりました。 暖かくなったんだなあという実感半分、煩わしい半分といったところでしょうか。 暖かくなるとこのように虫がでてきます。 特に夏場のキッチンなどは要注意。コバエの被害に苦しむ家庭も少なくないでしょう。 家庭でもよく見かけるこの「コバエ」ですが、 作った料理にとまってしまった!という経験はありませんか? そんな時あなたはどのように対処しますか。 私も経験があります。 サラダにとまったので、とまった半径3㎝ほどの範囲のサラダと上に乗っていたハムを捨てました。 この時の対応は様々で、気にせずに食べてしまうという人と、とまった範囲をよける人、全くその料理そのものを処分してしまう人と色々いるようです。 コバエは汚い排水溝やトイレ、ごみ置き場や腐った食材などに生息しています。 そのため、足をはじめとして体に細菌がついている可能性があります。 とまった料理を汚染させてしまうことも考えらえるでしょう。 しかし、料理に数秒とまった程度では健康被害が出ることは無いと考えられています。 実際そのような文献も見当たらないようです。 ですから、結論から言うと、「リスクはゼロではないがそのまま食べても問題はない」ということです。 実際作った料理や食材を捨てるというのは罪悪感もありますし、 そこまで気にしなくてもいいのかもしれません。 しかし、とまったという事実に嫌悪感を覚えるため、食べたくないという人もいるでしょう。 コバエならまだしも大きいハエならどうでしょうか。 少し止まっても健康被害がないから大丈夫、かもしれませんが今まで発表がないだけでリスクがゼロであるとは言い切れません。大きいハエであればそれだけリスクも上がります。 また、上記のように感情的には気持ちの良いものではないはずです。 コバエがとまったらどうするか、ではなくコバエの発生源そのものを絶つことを考えたいですね。 ではコバエの発生を防ぐためにどのような対策をしたらよいのでしょう。 コバエは水回りのぬめりや生ごみに寄ってきます。 シンクをこまめに掃除したり、生ごみを溜めないようにしたりすることが大事です。 また、食材はなるべく料理直前に切る、そして食べる直前に調理をする、長時間テーブルに放置しないなども気を付けたいところです。 お店と家庭での対応の違い コバエをはじめとして、ハエが少しくらい食事にとまっても問題ないことが分かりました。 しかし、家庭では少しくらいのリスクをとるのは自己責任で済ますことが出来ますが、店舗だとそうもいきません。 少しでも健康被害のリスクが考えられるならばそれらの要素は全て排除するべきです。 確かにハエがとまったことによる健康被害は今まで報告されていないかもしれませんが、先ほども書いたようにリスクがゼロというわけではありません。 もし作った料理や食材にハエがとまるなどがあれば、勿体ないですがそれらは処分してください。 コバエをはじめとした虫は様々な病原菌を持っており、人間への感染経路となることも少なくありません。 これはもちろん動物にも言えることです。 お店への動物の立ち入りは極力避けるようにしましょう。 つい最近某牛丼チェーン店でネズミの混入が問題となりました。 消費者がグーグルレビューにネズミが混入したみそ汁の写真を投稿し、それがXなどSNSで拡散され大炎上。 会社は謝罪文章を公表、その数日後には害虫混入の報告もあったため全店一時閉鎖にまで至りました。 害虫・害獣その他異物の混入は、その嫌悪感から客足が遠のくのではないかという懸念はもちろん、 他のお客さんに健康被害が出る可能性もあるので、特に気を付けなければなりません。 例えば、ネズミが混入していた場合にはどのような健康被害が考えられるのでしょうか。 ネズミの生息場所は地中や排水管、天井裏などです。そして下水溝や床下などを移動します。 そのため体にはたくさんの汚れや病原菌が付着しています。 それだけでなく、ネズミ自体が菌やウイルスをもっているので、嚙まれたりフンや尿などに触れたりするだけで病気にかかってしまうことがあります。 鼠咬症という噛まれて起こる病気や、ツツガムシ病という触れることで起こる病気では、死に至ってしまった人もいるのです。 このように、健康被害が出てしまった場合どのように責任を取るのでしょうか。 不十分な衛生管理から閉店に至ってしまった店も実際に存在しています。 このように、一回でも混入を許してしまうと、多大な被害を被ることが考えられます。 食材保管時の衛生管理やキッチン、ホールの清掃・消毒はしっかりと行ってください。 日々の掃除だけでなく、業者を入れた月に1回~数ヶ月に1回のクリーニングなどもおすすめです。 お店は家とは異なり、侵入経路が沢山あります。 使う食品の量も圧倒的に多いので、完全に発生を防ぐというのはかなり難しいかもしれません。 しかし、その可能性をゼロに近づけることは可能です。 しっかりと対策を行ってくださいね。
-
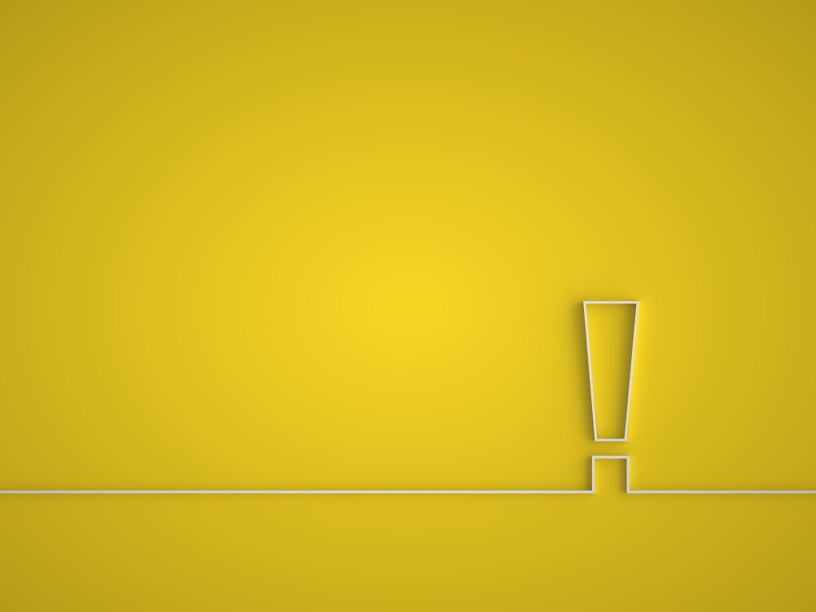
それ、ハラスメントかも。気を付けたいコンプライアンスのこと【店舗の開業なら塊】
「ハラスメント」とは こんにちは。 株式会社塊です。 昨今どんなことでも「ハラスメント」になってしまう時代。 先日聞いて驚いたのが「マルハラスメント」というもの。 どういったものかご存じでしょうか? マルハラスメント、通称マルハラとは句点の「。」に対して圧を感じるというハラスメントだそうです。 文章の終わりに句点の「。」を付けるのは当たり前な気がしますが、今の若い世代の中には句点がついていると、威圧感を感じて嫌な気持ちになったり怖く思ったりする人がいるんだとか。 いまやハラスメントはその種類が50を超えるらしく、言動には細心の注意を払わなければなりません。 しかし、難しいのは相手の判断に委ねられているところですね。 さて、そんなハラスメントですがもともとどういう意味で、いつ誕生したのでしょうか。 ハラスメント(Harassment)は英語で、意味は迷惑や嫌がらせ、悩ませることとあります。 英語がそのまま定着していることから分かる通り、ハラスメントはアメリカで最初問題視されました。その際はセクシュアル・ハラスメント、いわゆる職場における性的行動のことが取り上げられました。 その後1980年代後半に日本でも社会問題になり、1989年にははじめてセクシュアル・ハラスメントを問う裁判が行われました。 1990年代以降には、不況による職場内でのパワハラが問題視され始めました。 傷害などの肉体的な苦痛だけでなく、暴言やいじめなどの精神的苦痛もこの頃から問題となっています。 そして1998年にはモラハラという言葉が生まれます。 日本では最近になって特に問題視されるようになってきているように感じます。 少し前からは、カスハラ(カスタマーハラスメント)がよく取り上げられるようになりました。 今年(2025)の4月からは「東京都カスハラ防止条例」が施行することも決まっています。 そして今や、上記の代表的なハラスメントだけでなく、 「マタハラ(マタニティ・ハラスメント)」や「スメハラ(スメル・ハラスメント)」、「アルハラ(アルコール・ハラスメント)」などの聞いたことのあるハラスメントから 「マルハラ(句点ハラスメント)」、「オワハラ(就活終われハラスメント)」、「ハラハラ(ハラスメントハラスメント)」などにいたるまで様々なハラスメントが叫ばれているのです。 こう聞くと「何もできなくなってしまう」「面倒だ」と感じる方が多いでしょう。 しかし実際は法令対象になるハラスメントは少なく、そこまでおびえることはありません。 ですが、令和の時代に則って気を付けた方がいいことはあります。 店舗経営で気を付けたいハラスメント 店舗経営において気を付けたいのは以下のハラスメントになります。 ●カスタマーハラスメント 一番起こり得るのはこちらのハラスメントです。 これはお客さん→店へ向けたハラスメントになります。 お客さんが従業員に対して手を出したり、暴言を吐いたり、侮辱や差別的な発言をしたりなどがいま問題になっています。 実際に首を絞められた、殴られたという身体的な攻撃を受けた人もいます。 中には毎日無言電話を受けたり、人格否定の言葉を投げられたりして精神的に病んでしまった人もいます。 これらをうけて、北海道、群馬、東京都ではカスハラ防止条例を4月から施行します。 愛知、三重は制定する方針で、他5県でも制定を検討しているようです。 従業員や自分自身を守るためにも、カスハラを受けたときの対処法を考えておきましょう。 店内で対応マニュアルの共有をするだけでなく、弁護士や警察への相談も視野に入れなければなりません。 ●セクシュアルハラスメント これは経営者であるあなた→従業員の可能性が一番高いので気を付けましょう。 セクハラはなにも身体的な特徴をからかう、触るなどだけではありません。 「女にはこの仕事は任せられない」「男ならこれくらい食べれるでしょ」などの性別によって差別することもセクハラに該当します。 ほかには「おじさん」「おばさん」や「ちゃん」「くん」付けなど呼称にも気を付けて下さい。 これらも年齢を理由とした差別的な表現にあたる、セクハラの一種になります。 ●パワーハラスメント こちらも経営者→従業員、もしくは従業員の先輩→後輩が多いです。 自分が気を付けるだけでなく、従業員間のパワーバランスにも気を配りましょう。 身体的暴力をふるう、または悪口など精神的暴力をふるうだけではありません。 同僚の前で一人を叱ったり、以前したミスについて繰り返し言及したり、ミーティングに特定の人だけ参加させないなどもパワハラにあたります。 また、飲み会への参加の強制やプライベートへの過剰な干渉もパワハラにあたります。 仲良くなろうと思ってプライベートのこと(出身地や出身校、家族の話や恋愛の話)などを詳しく尋ねるというのはやりがちなことなので、線引きをしっかりしましょう。 まとめ 「ハラスメント」という言葉がそこまで認知されていない時代を過ごしていた人たちからすれば、今のこの状況は雁字搦めで窮屈に感じるでしょう。 しかし、仕事という共通目標に向かっている仲間の尊厳が損なわれるようなことは本来起きてはならないことです。 過剰に恐れる必要はありませんが、お互い尊重しあって気持ちよく働けるような環境をつくってくださいね。
-

賞味期限が延びる?期限の見直しへ【店舗の開業なら塊】
そもそも賞味期限って? こんにちは。 株式会社塊です。 私がカナダにいたときに驚いたことがいくつかあるのですが、そのうちの一つが卵の賞味期限の長さ! 大体1ヶ月程賞味期限が設けられていました。 日本の卵の賞味期限は1週間半~2週間程度でしょうか。意外に短いですよね。 12個入りのパックを買ってしまうと賞味期限を切らしてしまうことがよくあります。 この賞味期限の長さの違いには、欧米諸国が生や半熟で卵を食べるという習慣がないことが大きな理由のようです。 日本人は半熟の茹で卵や目玉焼き、卵かけごはんなど生の状態のまま食べる機会が多いので短めに設定されているということですね。 さて、この「賞味期限」ですが、そもそもどのように設定されているのでしょうか。 賞味期限は現在、衛生上安全であると検査で証明された日数に「安全係数」という0.8以上の数字をかけて設定されています。 例えば美味しく安全に食べられる日数(=消費期限)の設定が100日で、安全係数が0.8だとすると、賞味期限は80日ということになります。 賞味期限はもともと消費期限とは異なるもので、少しくらい過ぎても問題がない日数が設定されています。 あくまでも「おいしく、一番いい状態で」食べられる期間のことを指しています。 賞味期限が延びる!フードロス対策へ さて、そんな賞味期限ですが、TV番組「ひるおび」のアンケートによると 「気にする」と回答した人が90%、「気にしない」と答えた人が10%でした。 日本人は衛生観念が高い傾向にあるので、特に気にする人が多そうです。なかには1日でも過ぎたら絶対に口にしないという人もいるようです。 ですが、中には過ぎていても全然気にしないという人もいるようでした。 3月18日の消費者庁の有識者検討会では、賞味期限を延ばすように企業へ求めて行くとして意見が一致。 今後は賞味期限設定が係数0.8の現在から、1へ近づけていくように変わっていくようです。 ここ最近は特にフードロスの問題が良く叫ばれています。 日本の食品ロスは523万トン(令和5年)で、世界ランキングでは14位に位置します。 1位は中国ですが、一人当たりに換算すると64キロで同率になるので、日本はかなり高い数値を出していると言えるでしょう。 そんなフードロス対策にもこの賞味期限延長は一役買いそうです。 飲食店やスーパーなどの小売店等お店や企業は、賞味期限が一日でも切れていたら提供することは出来ません。 その食品の係数が0.8で、まだ安全日数には20日猶予があるとしても提供することが出来ないのです。 食品の廃棄は、店舗経営の中で最も勿体ないお金であると言えるでしょう。 そのためになるべくロスや在庫を出さないよう、仕入れ量を調整する必要があるのですが、これがなかなか難しいです。 季節や天候、気温などの外的要因や周辺状況など、様々な要素から判断しなければならないからです。 今回賞味期限が延びることで、そういったリスクが少し緩和されるでしょう。 食品のロス量も減る為、利益に還元できるようになりそうです。 ノロウイルスなども流行っているので、食品の衛生管理には十分気を付けた上で、今回の延長を活かせるといいですよね。
-
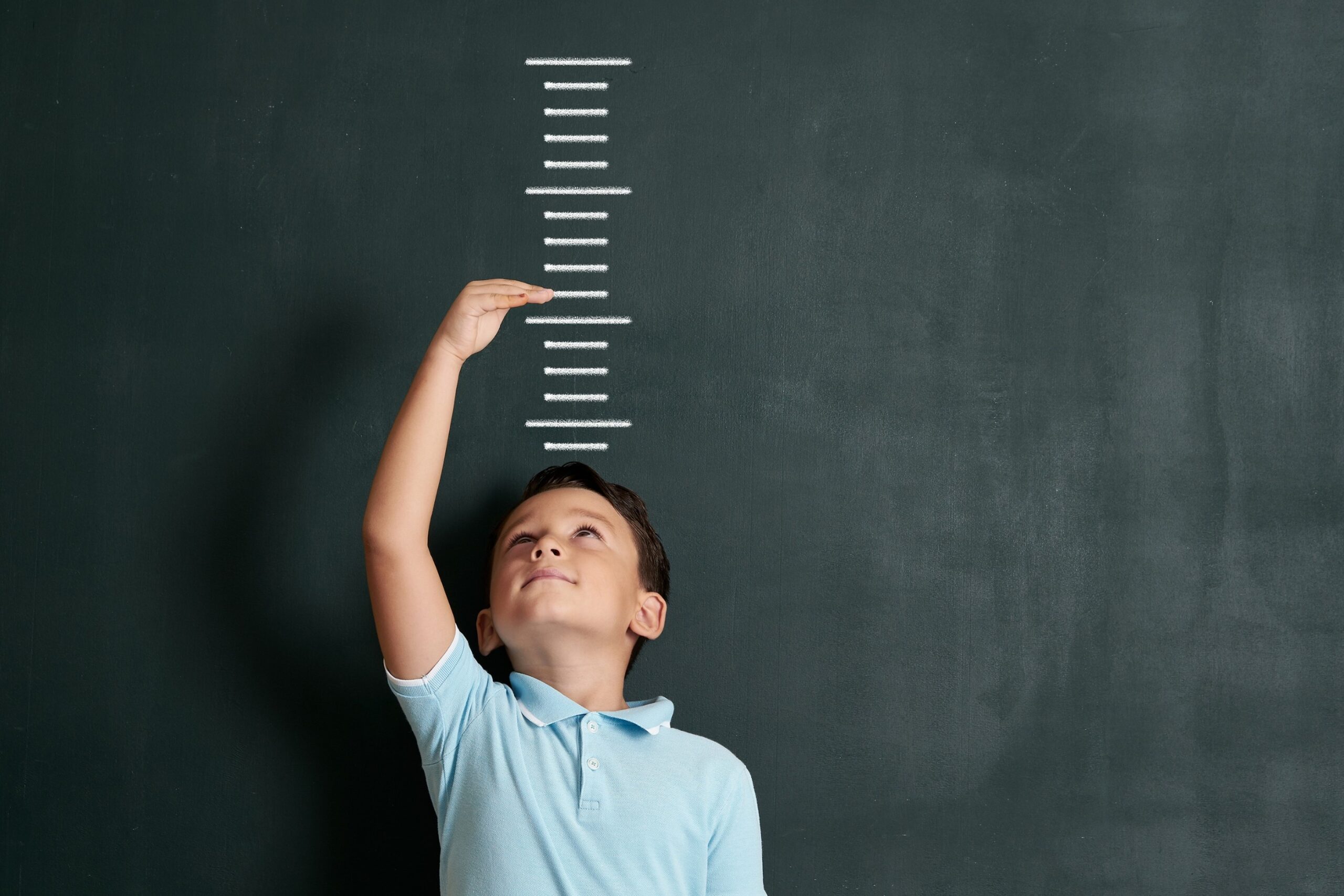
スタッフに期待をかけることで成果を出せる?【店舗の開業なら塊】
ピグマリオン効果とは こんにちは。 株式会社塊です。 「ピグマリオン効果」というのを聞いたことがありますか? アメリカの心理学者ロバート・ローゼンタールによって提唱されたこの現象は、 「人は、他者から期待されると期待に沿った成果を出す傾向にある」といったものです。 なぜ「ピグマリオン」という言葉がつけられたかというと、それはギリシャ神話に由来します。 ピグマリオン王が恋焦がれた女性の像が、その願いの力によって人間化したという逸話があり、 その願い(=期待)によってそれに沿った効果(=人間化)が現れるということからこの名前がつけられました。 では、実際にどのような実験が行われたのか見てみましょう。 1963年に大学教授であったローゼンタールとフォードが心理学の実験を行いました。 内容はネズミを使った迷路実験。 その際に、1つのグループには「これはよく訓練された利巧なネズミ」と説明して渡し、 もう1つのグループには「これはとてものろまなネズミ」と説明して渡しました。 すると、その2つのグループ間で実験結果に差が出たのです。 実際はネズミの知能程度や生育環境に違いはなかったのに、一体どういうことなのでしょうか。 前者の”利巧”なネズミを渡された学生たちは、ネズミをとても丁寧に扱いました。 しかし、後者の”のろまな”ネズミを渡された学生たちは、ネズミを非常にぞんざいに扱ったのです。 そこでローゼンタールは、学生たちのネズミに対する期待が結果に反映したのではないかと考えました。 そこで、翌年サンフランシスコの小学校で、ハーバード式突発性学習能力予測テストと名付けた普通の知能テストを行ないました。 学級担任には、今後数ヶ月の間に成績が伸びてくる学習者を割り出すための検査であると説明しました。 その後、学級担任にはこの検査結果には全く関係ない、無作為に選出した生徒を「数ヶ月の間に成績が伸びてくる生徒」として伝えました。 その後、その選出された生徒たちの成績が向上していきました。 実際には、選出された生徒たちの知能テストの結果は全員が優秀なわけではなかったのに、全員の成績が向上したこの実験について、ローゼンタールは以下のように考えました。 成績が向上した理由は、 ①担任が選出された子供たちに対して他の生徒よりも期待の目を向けていた点 ②担任の期待を受けて、子供たちの意識が変わった点 であるとし、論文を報告しました。 ピグマリオン効果を従業員教育に生かす 実際には、ローゼンタールが提唱したこのピグマリオン効果は後の再実験などで効果がみられなかったり、 教育現場にこの効果を用いたらえこひいきの助長になるのではと懸念されていたりします。 しかし、本実験以前に行われたホーソン実験でも、従業員の生産性が周囲からの期待や承認により高まるということが分かっています。 また、観察されている(注目されている)という意識が生産性に影響を及ぼすことも分かっています。 では、このピグマリオン効果を実際の従業員教育に生かしてみましょう。 これには費用も書類も時間もかかりません。 ただ、従業員に対して期待するだけでいいのです。 ですが、「期待してるよ」という声掛けや過度の期待は重圧となりプレッシャーになる可能性があります。 あくまでも、相手の負担にならない程度に期待をかけているということを伝えることが大事です。 例えば、仕事をお願いする際に「〇〇さんならできると思うから頼みたいんだけど」という接頭語をつけたり、 直接伝えるのではなく、第三者を通じて間接的に期待しているということを伝えたり、 やっている・やってきた作業に対してその成果を認めたりなど、 信頼している、期待を寄せているということが分かるよう、やわらかく表現できると良いでしょう。 最近では、「ホワイトハラスメント」なる言葉があるそうです。 これは過剰な配慮や優しさによって精神的な負担を与え、成長の機会を奪うというハラスメント=いじめや嫌がらせだそうです。 このように期待されないことをハラスメントだと感じる人がいるというのは、相手(主に上の立場の人)から期待をされるとやる気が出るというピグマリオン効果が、無意識的に人間には備わっていて、自分の成果を高めるためにそれが必要だと考えているからかもしれません。 期待をするというのは、その人自身の能力を評価しているということでもあります。 ですから期待を受けると嬉しくなり、頑張ろうと思えるのでしょう。 その伝え方は少し難しいかもしれませんが、従業員を信頼し期待をするというのは今日すぐに出来ることです。 それでお店全体の雰囲気が良くなり、売り上げを上げることが出来ればとてもいいですよね。
-

賃金よりも人間関係が大事?職場の生産性を上げるには【店舗の開業なら塊】
ホーソン実験とは こんにちは。 株式会社塊です。 アメリカのウェスタン・エレクトリック社で1924年から1932年にかけて2万人を対象に行われた実験があります。 その名を「ホーソン実験」といい、従業員の作業効率・生産性には何の要因が影響を与えるのか調査しました。 ウェスタン・エレクトリック社は電機機器開発・製造をおこなう企業で、最盛期には4万人を超える社員を抱えていましたが、1996年に解散。 いまでも一部事業はノキアに継承されています。 この企業で一番最初に行われたのが「照明実験」です。 この実験では作業場の照明を暗くした場合と明るくした場合で生産性に違いが生まれるか調べました。 結果、生産性への関連性は認められませんでした。 次に行われたのが「リレー組立実験」です。 リレー(継電器)の組立作業において実験が行われたためこの名前になりました。 リレー組立作業期間中に、休憩時間や労働日数、賃金などの労働条件を変えて生産性の変化を比較します。 この実験においては、労働条件が上がると確かに生産性の向上が見られました。 しかし意外だったのは、労働条件を元の悪いものに戻しても生産性が下がるなどの変化が見られなかったこと。 つまり結果として、労働条件は生産性と関連付けることができませんでした。 次に行われたのが「面接実験」です。 約2万人の社員を対象に、職場における不満や意見の聞き取り調査を行いました。 この結果分かったのは、従業員は賃金が高い・冷暖房が整っている・休日がしっかりとれるなどの労働条件ではなく、 この仕事が好き、楽しい、興味があるなどといった個人の好みや感情によってモチベーションが高まることが分かりました。 また、労働意欲・生産性には賃金などの労働条件ではなく、職場の人間関係が大きく影響することも分かりました。 最後に行われたのが「バンク配線作業実験」です。 バンク(電話交換機)の配線作業における実験です。 従業員を職種ごとに分け、集団での作業における生産性の変化をみました。 この結果、従業員同士の人間関係が作業に影響していることが分かりました。 また、上司と部下の関係が良好なグループほど、ミスが少なくなるということも分かりました。 ウェスタン・エレクトリック社におけるこれら4つの実験において、 労働者のモチベーションや生産性には労働条件などの外的要因ではなく、上司と部下など従業員間の人間関係や主観的な仕事に対する好みなどといった内的要因が影響を与えることが分かったのです。 職場の人間関係を良好にするには 高い賃金や福利厚生の充実なども大事ですが、それ以上に職場における人間関係が大事であることがこの実験から分かりました。 では、職場の人間関係を良くするにはどうしたらいいのでしょうか。 まず大事なのは、スタッフひとりひとりの性格をよく知ること。 最近では入社時に16パーソナリティ診断を設ける会社が増えましたが、このようなツールをつかってその人を把握する手助けにするというのも手です。 ひとりひとりを良く知れば、向いていそうな作業や合いそうな人が見えてくるはずです。 そしてあなたが配置していってください。 そして、定期的にひとりひとりと面談出来ると尚良いです。 仕事や同僚に対する不満や意見を聞いて、そこからまた配置やシフト変更などを行ってください。 他には、皆で共通の目標を掲げたり、仲良くなれるようなイベントを企画するのもいいです。 共通目標を掲げるのは帰属意識や責任感にも繋がりますし、イベントなどにはイレギュラー対応が求められるので、仕事を通して仲を深めることが出来ます。 イベントは基本的にお客さんに向けたものを企画しますが、実はこのように従業員同士の関係性を深めるためにも一役買うことになるのでおすすめです。 飲み会などを企画するのもいいですが、これには注意が必要です。 最近よく問題になるこの「職場の飲み会」ですが、従業員の中には嫌悪感を抱く人もいます。 株式会社R&Gの「職場の飲み会に関する意識調査」によると、なんと約74%の人が会社の飲み会には参加したくないと思っているんだとか。 お店と企業ではまた少し異なるとは思いますが、業務時間外での飲み会や食事会の開催には気を付けなければなりません。 良好な人間関係は、生産性だけでなく個々人の精神にも良い影響をもたらします。 ぜひいろいろな取り組みを試してみて下さい。
-

スタッフ教育は必要なのか【店舗の開業なら塊】
アルバイトに教育は必要? こんにちは。 株式会社塊です。 春は人の異動がある季節ですね。 なので本日は新人社員、アルバイトなどスタッフについての話をしたいと思います。 一般的に会社において、新人が入社すると「教育担当者」をつけるところが多いと思います。 会社における仕事は多岐に渡り、煩雑で複雑であることが多いので、 誰か長期間に渡って教えてくれる先輩が必要になってくるからです。 しかし、飲食店や小売店のアルバイトはどうでしょうか? もちろん業務は単純なものだけでなく様々なものがありますが、 ある程度の知識と経験がある人であれば、1日の簡単な説明で何とかなることが多いです。 これはキッチン作業などの調理は除き、ホールスタッフの場合の話です。 一般的には数週間~数ヶ月は研修期間を設けているお店が多く、 その間は時給が下がったり待遇が下がったりしますが、ある程度の失敗も許容され、 その間に慣れて覚えていってもらうことを意図します。 つまり実地で訓練を積ませるお店が多いのです。 練習をさせたり、教育担当者を設けているというお店はあまりないでしょう。 そもそもアルバイトにはそこまで労働に対する責任を負う必要がないので、 お店側もあまり多くのものを求めないというのが正しい姿勢ではあります。 そういった、数ヶ月~2,3年程度の限定的な期間の雇用が想定されるスタッフに対して、 そこまで人的リソースを割ける余裕がないというのも現状です。 しかし、ほんとうに教育担当者やトレーニングを設けなくてよいのでしょうか。 スタッフの離職率を下げることが結果として利益・売上アップに? 確かに、アルバイトやパートに対してそこまで人的リソースを割くのは難しいかもしれません。 しかし、相談役の先輩を置くことがスタッフの離職率を下げることも分かっています。 アメリカで行われた「ホーソン実験」というものがあります。 これは、人が生産性を高めるためにどのような要素を重視するのかという実験で、 2万人のスタッフを対象に行われました。 では、生産性向上に最も寄与するのは何の要素だと思いますか? 職場の物理的な環境でしょうか、人間関係でしょうか、仕事へのやりがいでしょうか? やはり賃金なのでしょうか? 驚くべきことに、生産性の向上には賃金などの待遇や職場環境よりも、人間関係の方が影響を与えることが分かっています。 スターバックスはアルバイトスタッフの離職率が驚くほど低いのだそうです。 殆どの方が大学1年生から4年生の卒業時まで勤め上げるのだとか。 面接はハイレベルと言われており、しっかりと人を見極めて判断します。 そのため、人間関係が良好な職場が多いんだとか。 これは、スターバックスの社風である「サードプレイス」(職場、家、そして第三の環境を提供する)というものとも関わりが深そうです。 新人に対して人的リソースを割く余裕がなく、新人教育を疎かにしがちであるというのが現状であるお店・企業が多いと思いますが、 実は教育担当者を付けてしまった方が、結果的に割く人的リソースが少なくなることがあります。 例えば、スタッフの離職率が高いお店で、半年の間に人が5人入れ替わるとしましょう。 先輩スタッフは、その6ヶ月の間に最低5回はアルバイト内容の説明を行わなければなりません。 教育担当者という制度ではないので、ずっと面倒をみなければならないという訳ではありませんが、半年で5回の説明はなかなか大変です。時間もかなりとられるでしょう。 では、離職率の低いお店で、半年で1人の新人スタッフだとしたらどうでしょうか。 初めはつきっきりでしっかりと仕事を教える必要がありますが、1・2ヶ月もすると一人で動けるようになるでしょう。 教育担当者という立ち位置ではありますが、最初の数か月を過ぎればそこまで手間もかかりません。 果たしてどちらが人的リソース、時間的リソースがかかっているのでしょうか。 スタッフの離職率が下がると、このように人的リソースも時間的リソースもかからないので、利益や売上が高まることも分かっています。 現場に慣れたスタッフでお店をまわすことができるので、高品質なサービスを提供することができ、顧客満足度も高まります。 まさに、スターバックスはそうですよね。 あの短い注文の時間でやりとりをして、お客さんに最適な提案をし、カップに絵柄やメッセージを書くなどの心遣いもあります。 このようなきめ細やかなサービスが、スターバックスが人気である理由の一つであると言っていいでしょう。 まとめ スタッフの新人教育はきちんと実施していないお店がほとんどです。 しかし、ここをしっかりと行うことで結果的に売上や利益が高まるかもしれません。 疎かにしがちな新人アルバイトへの対応ですが、一度ここでしっかりと考える機会にしてみてください。


